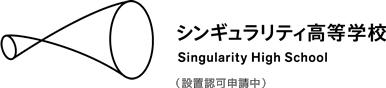eSOM (イゾーム)
eSOM (イゾーム)
Dへの道、あるいはシン高と幸和の物語
eSOM: Dへの道(35) 複雑系(リゾーム)、欲望(フロー)、そして東浩紀の偉大さ(1)
1.
現在、シン高では、三回目のスクーリング(対面授業)の真っ只中です。
これまでのところ、保健体育のベースは、私とチーフ・ファシリテーター(CF)である犬塚さんで構築してきました。
それがシン高における全ての学びの根本基礎となるからです。
いかなる意味で根本基礎なのか?
保健体育で探求する脳の構造と社会/世界の構造は、複雑系という点において共通しているからです。
Q.コロぴょん、脳の構造と社会ないし世界の構造が、複雑系という点で共通しているということを、詳しく論じてください。
『eSOM: Dへの道』(11)で紹介したドュルーズ&ガタリの概念「リゾーム」は基本、複雑系です。
Q. コロぴょん、複雑系が基本、ドゥルーズ&ガタリの概念「リゾーム」であることを詳解してください。
従って今後は、複雑系(≒リゾーム)と記述することにします。
複雑系(≒リゾーム)は、ワイル&タンの共著『Plurality』のキーワードの一つです。
例えばそれは次のような形で登場します:
「なめらかな社会とは、テクノロジーによって人間の認知の限界を越えたシステムを創造し、人々が複雑系を最大限に活かして生きることができる、よりネットワーク的な社会を生み出すビジョンである。」(178)
「なめらかな社会(Smooth Sciety, SS)」とは、『なめらかな社会とその敵』の著者・鈴木健さん(人工生命研究者・起業家)が唱える概念です。
この場合の複雑系(≒リゾーム)とは、「鈴木は、世界を複雑な網の目のようなネットワークとして理解している」(178頁)と言った場合の、「世界=網の目のようなネットワーク」の「(動的で、非線形的で、創発的、そして非階層的な)関係性のパターン、組織化の原理」と言えるでしょう。
Q.コロぴょん、複雑系(≒リゾーム)が、「世界=網の目のようなネットワーク」の、「(動的で、非線形的で、創発的、そして非階層的な)関係性のパターン、組織化の原理」であるということを、詳しく説明してください。
なにやら難解な言葉が並んでいますが、こうした言葉から複雑系(≒リゾーム)をイメージするのが難しかったら、「体育」の授業で学んだ、偏桃体やら、HPA軸システムやら、コルチゾールやら、海馬やら、前頭葉やら、GABAやら、「ニューロンの乳母」やらが、脳内で複雑に関係し合った、ストレスとその調節のメカニズムを思い出してみましょう。(『eSOM』33、34参照)
ストレス一つとってもあれだけ複雑な「(動的で、非線形的で、創発的、そして非階層的な)関係性のパターン、組織化の原理」。
あれが「複雑系(≒リゾーム)」です。
脳を(マイクロ)社会世界とするなら、一つ一つの部位は人間一人ひとりということになるでしょう。
一つひとつの部位が、脳や身体全体の他の部位と分かち難く、「動的で、非線形的で、創発的、そして非階層的な」関係を持っています。
社会と個人は、そのようなものとして存在しているというのが『Plurality』の主張です。
2
いずれにせよ、まず、「複雑系(≒リゾーム)」という「関係性のパターンないし組織化の原理」を持つ「世界(=網の目のようなネットワーク)」が存在します。
その「「関係性のパターンないし組織化の原理」」を、「テクノロジーによって」「最大限に活かして生きることができる、よりネットワーク的な社会」=「人間の認知の限界を越えたシステム」が、SSということになるでしょう。
こうした意味でのSSは、言うまでもなくタンさんが唱える「デジタル民主主義(DD)」であり、つまりは我々にとっての「交換様式Dを基にする社会(D)」ということになります。
SS≒DD≒Dなわけです。
では、SS≒DD≒Dは、タンさんの言うプルラリティ(多元性)とどのように関係するのでしょうか。
『Plurality』はプルラリティ(多元性)という概念を「社会的差異を越えたコラボレーションのための技術」と定義します。(116頁)
この場合の技術とは、鈴木さんにおける「テクノロジー」であり、そしてまたそれはハイデガーの言う「テクネ―(技術)」(「ゲシュテル(技術)」と異なる)である考えられます。
Q. コロぴょん、ハイデガーが「テクネ―(技術)」をどのように論じたかを、詳しく教えてください。
コロぴょんの答えの中の、テクネ―(技術)とゲシュテル(技術)の違いが我々にとって大重要になります。
言うまでもなくテクネ―(技術)が、「社会的差異を越えたコラボレーションのための技術≒プルラリティ≒多元性」です。
それは、複雑系(≒リゾーム≒関係性のパターンないし組織化の原理)を「最大限に活かして生きることができる、よりネットワーク的な社会」=「人間の認知の限界を越えたシステム」の生成に役立ちます。
この「よりネットワーク的な社会」=「人間の認知の限界を越えたシステム」がSS(なめらかな社会, Smooth Sciety)であり、従ってDD=Dです。
テクネ―(≒プルラリテ)が「D≒DD≒SS構築のための技術」であるのに対し、ゲシュテル(技術)は「BないしC構築のための技術」と言えるでしょう。
Bとは「交換様式B」および「交換様式Bを基にする社会」のことであり、Cとは「交換様式C」および「交換様式Cを基にする社会」のことです。
テクネ―としての技術(Dのための技術)と、ゲシュテルとしての技術(BないしCのための技術)の典型が貨幣制度です。
Q. コロぴょん、貨幣制度は一つの技術(テクノロジー)であり、テクネ―(技術)に対するゲシュテル(技術)であると言ってよいですか?
貨幣制度はゲシュテル(BないしCのための技術)であることを前提とした私の質問に対し、貨幣制度はゲシュテルのみならずテクネ―(AないしDのための技術)にもなり得るというコロぴょんの答えは、様々な意味で最良なものとなっていますので、必ず熟読しておいてください。
3.
プルラリティ(多元性)は、記述的(ハナ・アーレント)、規範的(ダニエル・アレン)、処方的(オードリー・タン)という3つの側面を持ちます。
タンさんによるプルラリティの「処方的側面」は、次のように定義されます:
「処方的(側面):デジタル技術は、産業技術が物理的な燃料を利用しての爆発を封じ込めるエンジンを作ったのと同じように、多様性の暴発を活用す3るエンジンの構築を目指すべきだ。」(118頁)
これは次のように翻訳可能でしょう:
「ゲシュテル(BないしCのための技術)は、対立/分断さえ生成させかねない多様性(≒複雑系≒リゾーム≒関係性のパターンないし組織化の原理)の爆発を活用するようなテクネ―(Dのための技術)となることを目指すべきだ」
これと関係するプルラリティの「規範的(側面)」は、ダニエル・アレンの論考をもとに次のように定義されます:
「(プルラリティ/多元性の)規範的(側面):多様性は社会進歩の原動力であり、他の原動力と同様に爆発する(対立に発展する)可能性はあるが、社会が成功するためには、その潜在的なエネルギーを成長のために活用しなければならない。」(117―8頁)
これらプルラリティの両側面で、プルラリティ(≒テクネー)がD/DD/SSの生成のため活用出来るようにすると言われる「多様性/複雑系/リゾーム」と「エネルギー」は、どのような関係にあるのでしょうか?
結論から言うと、ここでの「エネルギー」とは、ドュルーズ&ガタリ(DG)の言う「欲望」(フロイト/ラカンのそれとは根本的に異なる)であり、それはDGの言う「リゾーム(≒複雑系≒多様性≒関係性のパターンないし組織化の原理)」と考えられます。
Q. コロぴょん、ドゥルーズ&ガタリにおいて、彼らの言う「リゾーム」が、彼らの言う「欲望」そのものであるということを、詳しく説明してください。
コロぴょんの答えを基にすれば、リゾーム(≒複雑系≒関係性のパターンないし組織化の原理)と言った場合の「関係性のパターンないし組織化の原理」とは、「欲望が常に新たな接続を生み出し、異質なものを取り込み、固定された中心を持たずに遍在し、流動的に変化していくそのあり方」、「欲望が世界中でどのように機能し、どのように増殖していくかを記述するためのモデル」、「既存の秩序やカテゴリーに収まらない、常に生成変化する力」としての「欲望の具体的な発現形式」ということになります。
「「既存の秩序やカテゴリーに収まらない、常に生成変化する力」としての欲望は、一つの運動体であり、この運動体としての欲望をDGは「欲望機械」と呼んだわけです。
リゾームは、そうした欲望機械(=運動体=欲望)の運動の「あり方」、そうした運動を「記述するためのモデル」、かつ、そうした運動の「具体的な発現形式」ということになります。
それゆえコロぴょんは、「リゾームは既存のものを再現するデカルコマニー(写し)ではなく、常に新たな可能性を探り、構築していく地図のようなもの」ということになるわけです。
こうした欲望(機械)=運動体=複雑系=多様性としてのリゾームを、SS≒DD≒Dの生成に活用出来るようにするのが、技術(テクネ―)としてのプルラリティ(多元性)というわけです。
(続く)