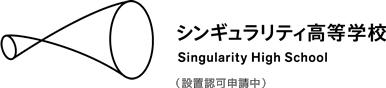eSOM (イゾーム)
eSOM (イゾーム)
Dへの道、あるいはシン高と幸和の物語
eSOM: Dへの道(34)ストレス、フローの最大の敵 Part 2
1
脳には、海馬と前頭葉という、「ストレス反応を緩和して、興奮やパニック発作を防ぐブレーキペダル」が備わっています。
それに対し偏桃体は、「脳のアクセル」と見做すことが出来るでしょう。
ブレーキ1:海馬について
-
海馬は「記憶の中枢」として有名だが、ストレスを低減する役割も担う。(68~9頁)
-
コロぴょん、海馬はどのようにしてストレス反応を低減するのですか?
-
「海馬には、コルチゾールに対する受容体(グルココルチコイド受容体)が豊富に存在します。コルチゾールが海馬の受容体に結合すると、海馬は視床下部へのネガティブフィードバックをかけ、CRH(副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン)の分泌を抑制します。これにより、コルチゾールの過剰な放出が抑えられ、HPA軸の活動が鎮静化されます。」
-
「海馬の細胞は過度のコルチゾールにさらされると死んでしまう」(70頁)
-
「偏桃体が長期にわたってストレス反応を引き起こしつづけると、海馬のブレーキはすり減ってしまう。そしてアクセルである偏桃体は、海馬が委縮してブレーキが利かなくなると暴走を始める。こうして、ストレスがストレスを生むという悪循環に入る。」(71頁)
-
「これがストレスが長引いたり慢性化したりするメカニズムである。長期的なストレスによって脳が損傷を受けるのは、この悪循環によるものだ。」(71頁)
ブレーキ2:前頭葉
-
「…前頭葉の前の部分「前頭前皮質」と呼ばれる領域は、高次認知機能をつかさどっている。たとえば衝動を抑えたり、抽象的思考や分析的思考を行ったりする、文字通り「高尚な場所」である。ストレスを感じているとき、前頭葉が感情が暴走しないように、また理性を失った行動に出ないように働いているわけだ。」(76頁)
-
「前頭葉の前の部分「前頭前皮質」」=コンピュテーショナル・シンキング(CT)の源泉としての「脳の司令塔」
-
海馬同様、前頭葉という「ブレーキ」も、ストレスによって摩耗(縮小)する。(77頁)
-
コロぴょん、海馬同様、前頭葉もストレスによって縮小するのは、どういったメカニズムによるものですか?
-
これも海馬同様、コルチゾールの分泌量の増大によるもの。
-
もう少し詳しく言えば、海馬の場合と同様に前頭葉の場合も、その内に含まれるコルチゾールに対する受容体(グルココルチコイド受容体、GR)がHPA軸にコルチゾールを抑制するよう働きかける(ネガティブフィードバック)。しかしGRが過度に活動し続けると、海馬の場合同様、前頭葉を構成する細胞の死を招く。
2
車の場合と同様に、ブレーキ(海馬、前頭葉)は使っていれば摩耗(縮小)します。
その摩耗(縮小)を最小限に抑え、それどころか時にはより高級なブレーキへとアップグレードするのが運動(ランニング/ウォーキング)です。
海馬の場合から順に見てゆきましょう。
運動と海馬の関係1:コルチゾールの分泌量の抑制
-
「定期的に運動を続けていると、運動以外のことが原因のストレスを抱えているときでも、コルチゾールの分泌量はわずかしか上がらなくなっていく。」(73頁)
-
「つまり運動が、ストレスに対して過剰に反応しないように身体をしつけるのである。」(73頁)
-
「身体を活発に動かしたことでストレスに対する抵抗力が高まるのであろう。」(73頁)
運動と海馬の関係2:抗ストレスニューロンの活性化
-
運動をすると脳に新しい神経細胞(ニューロン)が生まれる。(詳しくは第五章「「記憶力」を極限まで高める」で学びます。)
-
新しいニューロンは、まるで幼児のように活発であるため、脳の活動を活性化し、結果、ストレスを増幅する。
-
しかし、運動によって構築される新しいニューロンの中に、他の新生ニューロンの過剰な活動を抑制する抗ストレスニューロン「GABA作動性ニューロン(「ニューロンの乳母」)」が含まれている。
-
GABA=ギャバ、ガンマアミノ酪酸と呼ばれるアミノ酸(55頁)
-
「GABAは脳内の活動を抑制して変化を起こさないようにする、いわば「ブレーキ」の役目を担っている」(55頁)
-
「ニューロンの乳母」はGABAを放出する。
-
「ニューロンの乳母」は主に海馬(感情を制御して不安を鎮める役目を担っている部位)で生産される。
-
運動により、海馬において「ニューロンの乳母」が構築される。
-
同ニューロンが放出するGABAがコルチゾール(ストレス物質)の分泌を低減するという形で運動は、海馬の「扁桃体(アクセル)に対するブレーキ」としての機能をアシストする。
3
では、運動はどのようにして「もう一つのブレーキ(前頭葉)」の「効き」をよくするのでしょうか(=扁桃体/アクセルの暴走を制御するのでしょうか)?
運動と前頭葉の関係1:運動による血流の活性化と新しい血管の構築
-
「身体を活発に動かすと脳の血流が増える。前頭葉にたちまち大量に血液が流れ、機能を促進する。さらに、運動を長期にわたって続けると、やがて前頭葉に新しい血管がつくられ、血液や酸素の供給量が増え、それによって老廃物がしっかり取り除かれる。」(79頁)
運動と前頭葉の関係2:前頭葉と扁桃体の連携の強化
-
運動により、前頭葉と扁桃体の連携が強化され、前頭葉がより効率的に扁桃体を制御できるようになる。(79頁)
運動と前頭葉の関係3:運動による前頭葉の成長
-
「定期的に運動を続ければ、期間は長くかかるものの、前頭葉は物理的に成長までする」(79頁)
このように脳には元々、ストレスを緩和する「ブレーキ(海馬、前頭葉)」が備わっており、ランニング/ウォーキングは、その「効き」を良くすると同時に、その「摩耗」を低減したりします(「脳にはあらかじめ、ストレスを鎮めようとするプログラムが組み込まれている」)。(81頁)
それ以外に、人間の身体の外部に、ストレスを緩和する「ブレーキ」が存在します。
「抗不安剤(ジアゼパム、オキサゼパム、ロヒプノール、ザナックスなど)」と、アルコールです。
この二つの「外部ブレーキ」は、同じ方法でストレスを緩和します。
コルチゾール(ストレス物質)の分泌を低減するという形で、「ブレーキ1(海馬)」をアシストするギャバ
抗不安剤とアルコールは共に、GABA(神経伝達物質、ガンマアミノ酪酸)の働きを強め、コルチゾール(ストレスホルモン)の分泌を間接的に低減する形で、ストレスを緩和します。
上の「運動と海馬の関係2:抗ストレスニューロンの活性化」で登場したGABAですが、『運動脳』では、「運動が脳に与える影響において、GABAは矛盾した存在でもある」と書かれています。
なぜ「矛盾した存在」なのか?
なぜならGABAは、コルチゾールの分泌を抑制する形でストレスを緩和し、ストレスによる脳の縮小を防ぐ一方、「脳の成長を阻害する厄介者」(82頁)でもあるからです。
「GABAは脳内の活動を抑制して変化が起こらないようにする、いわば「ブレーキ」の役目を担っている」(55頁)というように、「脳の成長のブレーキ」でもあるというわけです。
しかし脳にとって良いことだらけのランニング/ウォーキングとは異なり、抗不安剤とアルコールは、脳や身体に深刻なダメージを与えかねません。
詳しくは「保健」の授業で学ぶとして、ここでは次の点を押さえておきましょう:
「…抗不安剤を一度でも試せば、脳がそれを渇望してしまう危険性がある。そのうえ、脳は薬にたちまち順応し、たとえ投薬の期間が短くても初めに安堵感をえられた量では足りなくなる。同じ効果を得るには薬の量を増やさなければならず、そうなると薬物依存にもなりかねない。
…薬のほうかにも、ストレスや不安を消し去ることにおいて驚異的な効果があり、依存症の危険性もきわめて高い物質がある。「アルコール」だ。」(81頁)
4
GABAが脳の構築において良い面と悪い面の両方があるの同様に、ストレスそのもののも、脳の構築において悪い面ばかりではなく、良い面もあります。
まずストレスには、神経を研ぎ澄ませ、集中力を高める役割があります。(66頁)
しかしそのストレスが過度になると、「集中力が高まるどころか、かえって思考が混乱してしまうのである。」(66頁)
またストレスは、闘争/逃走という形で危機を回避する効用があります。(91~9頁)
しかしそれが度を過ぎると、「偏桃体ハイジャック」が起こります。(99~100頁)
こうしたストレスの悪い面を最小化し、良い面を最大化するには、運動により脳の各部位の機能を活性化し、ストレスに対する脳の耐性を高めるというのが『運動脳』の結論です。(100~9頁)
最後に『運動脳』は、運動によってコルチゾール(不安物質)を制御する利点について、非常に興味深いことを述べています。
コルチゾールには「身体の脂肪の燃焼を妨げる作用」があるのだそうです。
つまり、運動によってコルチゾールの分泌を最適化することは、脳の構築に直接寄与するのみならず、その構築に不可欠な身体全体の構築に大いに寄与するというわけです。
(続く)