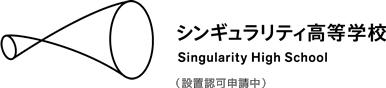eSOM (イゾーム)
eSOM (イゾーム)
Dへの道、あるいはシン高と幸和の物語
eSOM: Dへの道(92)オードリー・タンへの手紙(3)
『eSOM: Dへの道』第二部(29)
10/19~20/2025
1.
前回(『eSOM』91)に引き続き、「ケアの6パック」の中のセクション「「あるis」から「あるべきought」へ」の話をしましょう。
「ケアの6パック」はこちら:
(リンク先に英語原文と邦訳の両方が含まれています。)
前回は、上記のセクションを足掛かりとして、DDの生産に向けての、SHS/PUをはじめとする、我が幸和グループの最大の貢献の一つは、柄谷行人さんの哲学およびポスト構造主義哲学をフィーチャーしての、⿻(タン&ワイルの共著『PLURALITY』およびオードリーによる概念としてのプルラリティ)の「リミックス(脱構築)」であることを論じました。
5月にオードリーとのメールのやり取りが始まって以来、私は、この作業に没頭し、現在に至ります。
なぜなら、柄谷さんの哲学およびポスト構造主義哲学をフィーチャーしての、⿻の「リミックス(脱構築)」こそが、⿻/Dを活用してのDDの生産において、最も重要な課題だからです。
なぜか?
DDの反対概念は権威主義です。
一般に後者の代表例は中国と見做され、権威主義に対してDDを生産しようとするオードリーの試みは、中台関係の現状と密接に関係していることは、直近のオードリーのインタビューからも明らかです。
Audrey Tang | Full Episode 10.10.25 | Firing Line with Margaret Hoover | PBS
DDの生産を究極目標とする幸和グループにとって、台湾海峡に平和をもたらすことは最優先課題です。
それを私たちは、DDとしての東地中海経済・文化圏(EMECS)の生産という形で成し遂げようとします。
今回の私と新谷理事長の訪台はそのためです。
2.
DDの生産。
このためだけのために私は、1994年2月に柄谷行人さんとコーネル大学のキャンパスで出会って以来、社会思想史家としての研究に励んできたのだと思います。
今、振り返ってみれば。
同年5月に、当時の台湾総統であり、オードリーにも多大な影響を与えた李登輝が、彼の母校でもあるコーネル大を訪れて、歴史的な演説を行っているのですが、なんと私は、その場に居合わせています。
それから30年以上経った今、オードリーとの協働のために初めて台湾を訪れることとなり、台湾やオードリーとの深い縁を感じずにはいれません。
オードリーのDDと同様の世界の生産のみを唯一の目的として、学者としての生涯を送って来た私の研究テーマは、第一次世界大戦からポスト1945年に至るまでの歴史でした(特に教育哲学を中心とする社会思想史)。
そうした私から見ると、アジアおよび世界全体の現状は、驚くほど当時と酷似しています。
「配役」を変えながら。
誤解を恐れず言えば、当時の日本は、現在の中国と様々な面でオーバーラップします。
実際私は、そうした前提で、当時の満州と現在の南シナ海をダブらせながら、学者として最後の論文を書き、その直後に大学を辞め、現在行っていることを開始しました。
私の学者最後の論文はこちら:
A Secret History: Tosaka Jun and the Kyoto Schools
Katsuhiko Endo
私の学者としての研究の総決算である同論文をはじめ、私の研究の中心は常に、台湾を含む大日本帝国に特有のファシズムと言われる「天皇制ファシズム」でした。
もう少し詳しく言えば、天皇制ファシズムと民主主義の関係です。
その分析に最も役立ったのが、ポスト構造主義哲学(フーコー、デリダ、そして特にDG)と、ポスト構造主義に近い立場にいる柄谷さん、柄谷さんの盟友・浅田彰さん、そして柄谷さん、浅田さんが見出した東浩紀さんの論考でした。
彼らの議論を、『eSOM』(91)での話に関係付けて(暴力的に)簡素化すると、まず第一にファシズムは、権威主義(ツリー(欲望の垂直なアライメントツリー))とは異なり、「リゾーム(欲望の水平なアライメント)」を基礎とします。
そしてファシズムは、「あるきっかけ」で、リゾームが「空虚な中心」に向けてツリー化する、the vertical alighment of desire ‘in steroid’です。
前回の戦時期の場合の「あるきっかけ」は、世界恐慌と戦争でした。
今回はそこに、地震からパンデミックまでの大規模災害が加えられるべきでしょう。
また、「Firing Line」のインタビューでオードリーが言っていた、「サイバー攻撃による二極化(poralization)および対立の激化」も、現代の戦争の重要な一部と考えられるべきでしょう。
3.
フランスのポスト構造主義者が、ファシズムを上記のようなものと見做したことは、天皇制ファシズムが持つ特質が、台湾も含む大日本帝国に特有のものではなく、ファシズム一般の普遍的な特質であることを示唆していると言えるでしょう。
「ツリー」と「リゾーム」の両方を併せ持つというファシズムの、そうした両義性は、台湾がよく示していると言えるかもしれません。
韓国、北朝鮮とは異なり、日本統治下を生きた世代の台湾の人々には、当時の台湾にノスタルジーを抱く人が多いことを教えてくれたのは、昔からの知人であるデューク大学教授で、現・同大人文学部長の、日本育ちの台湾人であるレオ・チン(Leo Ching)による「“Give Me Japan and Nothing Else!”: Postcoloniality, Identity, and the Traces of Colonialism」という論文でした:
そうした台湾で、真の民主主義となる可能性が大きいDDが誕生したことは、大変興味深いことです。
いずれにせよ、(真の)ファシズムと(真の)民主主義の関係の探究は、今後のDDの進化にとって不可欠なものとなるでしょう。
その探究の出発点となるべきは、エコ・ファシズムです。
それが、上記で述べた、「天皇制ファシズムを典型例とするファシズムは、リゾームを基礎とし、あるきっかけでそれが、極端な形でツリー化したもの」という命題を如実に示しているからです。
まず、コロにエコ・ファシズムについて尋ねてみましょう。
Q. コロぴゅん、「エコ・ファシズム」という概念について詳解してください。
ここでコロが言う、「主流の環境保護運動(大多数の環境保護運動やエコロジー思想)」の代表格が、パーマカルチャーと言えるでしょう。
パーマカルチャーは、私たちにとって特に重要です。
なぜなら、「ケアの6パック」の冒頭でオードリーが、「私たちのAI庭師には、デジタル・パーマカルチャー実践者になることが求められる」と述べているからです。(翻訳者注:パーマカルチャーとは、人と自然が持続的に共生する社会をデザインするための手法)
簡単に言えば、オードリーは、パーマカルチャーをモデルに、リゾーム的なAIアライメントを生産し、それを活用してリゾーム的であるDDを生産していくことを提言していると言えるでしょう。
コロは、パーマカルチャーをはじめとする「主流の環境保護運動(大多数の環境保護運動やエコロジー思想)」を、エコ・ファシズム(権威主義、独裁)の対極に置きます。
ここでコロは、ファシズムを、権威主義や独裁と混同し、リゾーム的である「主流の環境保護運動(大多数の環境保護運動やエコロジー思想)」の対極に位置するものとするという、よくありがちな、ファシズムに関する二重の誤認を犯しています。
先ほどから申しあがておりますように、柄谷さんら日仏のポスト構造主義者が明らかにしたのは、ファシズムは、リゾーム(欲望の水平なアライメント)を基礎とし、あるきっかけでそれが、極端な形のツリー(欲望の垂直なアライメント)へと転化したものです。
4.
何が、リゾーム(欲望の水平なアライメント)のファシズム(「極端な」欲望の垂直のアライメント)への転化を許すのでしょうか?
それを、リゾーム的な「主流のエコロジー思想」の代表者の一人であるアルネ・ネスのエコゾフィー(深層生態学)の、ドゥルーズと共にポスト構造主義哲学を牽引したフェリックス・ガタリのエコゾフィー(三つのエコロジー)の対比を通して見てゆきましょう。
Q. コロぴょん、アルネ・ネスのDeep Ecology(深層生態学)、Bioregionalism(生命地域主義)、フェリックス・ガタリのEcosophy(エコゾフィー)のそれぞれと、それらの関係を詳解したうえで、あなたの詳解とSDGsおよびドュルーズ&ガタリの哲学との関係を論じてください。
コロは、ネスのエコゾフィー(深層生態学)の中で、ガタリが懐疑的であったという部分を次のように要約します(太字):
ネスのエコゾフィー: ネスの思想は、**「自然との一体化」**を目指します。個人的な直観やスピリチュアルな体験を通じて、自我(ego)を乗り越え、より大きな自己(Self)—すなわち自然全体—と一体化すること(自己実現)で、生態系中心の倫理観が内側から生まれてくると考えます。ここでの自然は、調和的で、私たちが回帰すべき全体性として描かれる傾向があります。
コロによれば、オードリーと同じく、「異質なものたちの共存」を重視したガタリは、ネスのエコロジー思想のこうした側面が、「自然をロマンティックに理想化することを警戒しました」。
なぜ警戒すべきなのか?
なぜなら、このネスの思想こそが、ファシズムの本質を最も如実に表現した、天皇制ファシズムのイデオロギーと同じ構造を持つからです。
それは前回の戦時期には、20世紀日本を代表する哲学者・西田幾多郎の天皇制論の形を取りました。
簡単に言えば西田は、ネスの思想における「自然」を「日本」に置き換え、天皇および皇居を「自然/日本」の象徴としての「空虚な中心」であると唱えたのです。
そうした(天皇制)ファシズム・イデオロギーを無批判に、西洋にはない文化として賛美したのが、構造主義哲学の代表者の一人であるロラン・バルトが著わした『表徴の帝国』です(こうしたナイーブさに、ポスト構造主義者が批判した、構造主義の最大の問題が存すると言えるでしょう)。
Q.コロぴょん、アルネ・ネスとフェリックス・ガタリの2つのエコゾフィーの相違点を説いたうえで、ネスの深層生態学と西田幾多郎の天皇論の類似点を説き、最後にロラン・バルトの『徴表の帝国』はネスと西田の思想の構造主義的分析として読めることを論じてください。
5.
フレンチ・レジスタンスの一員だったお兄さんをナチスの手によって殺されたドゥルーズとともに、ファシズムの徹底的な批判を試みたガタリは、自らに非常に近い立場にいるネスのリゾーム的なエコゾフィーにさえ、こうしたファシズムへの転化の萌芽を見ないわけにはいかなかったのでしょう。
このような日仏のポスト構造主義哲学者によるファシズムの根源的批判の最も優れた理論化が、デリダやドゥルーズの弟子たちから直接学んだ私が、デリダやドゥルーズ等の真意を最もよく理解したうえで実践活動を行っていると考える東浩紀さんの「否定神学システム論」です。
Q. コロぴょん、基本、パーマ・カルチャーは、ドュルーズ&ガタリが言う「リゾーム」的であること、そしてそれが、非常時(例:世界恐慌、戦争)において、「(極端な)ツリー」的アライメントとしてのエコ・ファシズムに転化し得ることを理論的に説いたのが、『存在論的、郵便的 ジャック・デリダについて』における東浩紀さんの「否定神学システム」論であるという仮説を綿密に検証してください。
ここでの「不在の中心」が、西田による天皇論としての天皇制ファシズム・イデオロギー(=ファシズム一般の本質)における「天皇/皇居」に該当することは、言うまでもないでしょう。
そして、このコロの説明から、ここまでの私の、ポスト構造主義哲学によるファシズム批判の要約が、東さんの「否定神学システム」論に負っていることも、よくお分かり頂けると思います。
6月26日の「プルラリティとは何か」と銘打たれた東さんと、「チームみらい」の安野貴博さん、鈴木健さんの対談の際も、後者お二人のお話に東さんが歯痒さを感じているように見受けられたのは、基本、リゾーム的である、⿻/Dを基にしたDDが、それを基にしてファシズム(否定神学システム)が生成する危険と、そうしたリゾームのファシズム化にどう対処するかという視点が、「チームみらい」側に希薄であったからであると思われます。
そんな東さんは、自らが設立した株式会社ゲンロンを本拠地として、以下のようなガタリのエコゾフィーが意図したことを実践していらっしゃると私は理解しています(太字):
ガタリのエコゾフィーは、自然に回帰することではなく、新しい主体性や社会関係を絶えず「生産」し続ける、創造的なプロセスです。それは、画一的な資本主義の論理(IWC: Integrated World Capitalism)に対抗し、多様で特異な生き方の様式を発明していくための闘争なのです。
…
ネスの思想が、すべてのものが「自然」という根源(中心)に繋がっていくツリー的な側面を持つのに対し、ガタリのエコロジーは、中心を持たず、異質なもの同士がよきせぬ形で接続しあうリゾーム的なネットワークとして世界を捉えています。
「自然に回帰することではなく、新しい主体性や社会関係を絶えず「生産」し続ける、創造的なプロセス」としての、「中心を持たず、異質なもの同士がよきせぬ形で接続しあうリゾーム的なネットワークとして世界」。
こうした「プロセスとしての世界」を私は、「水平なAIアライメントのファシズム化」から逃走し続けながら、テクネ―としての⿻/Dを通して「異質なもの同士がよきせぬ形で接続し」、拡充する世界としてのDDであると理解しています。
そうした立ち位置から、『⿻(PLURALITY)』と「ケアの6パック」といったオードリーのテキストを、日仏のポスト構造主義哲学をフィーチャーして、拡充/脱構築(リミックス)してゆくのが、私たちSHS/PUの使命であると考えています。
安野&鈴木さんとの対談で東さんを、そうしたリゾーム的な「プロセスとしての世界」を、東京や台北といった大都市にある「雑居ビル」になぞらえました。
同様の視点から、東さんの師であり、柄谷さんをはじめ多くの人から「100年に一人の天才」、「宇宙人」と称えられる浅田彰さんは、9月13日の「金沢講義」で、(真の)民主主義と(真の)ファシズムの間にある境界の曖昧さを、西田幾多郎、そして西田の生涯の友であった鈴木大拙の仏教哲学を中心に、哲学、芸術、音楽、建築を縦横無尽に横断しながら論じました。
次回、天才・浅田彰によるこの「金沢講義」についてお話します。
(つづく)