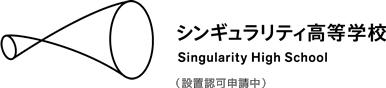eSOM (イゾーム)
eSOM (イゾーム)
Dへの道、あるいはシン高と幸和の物語
eSOM: Dへの道(38)リゾーム(複雑系)、欲望(フロー)、そして東浩紀の偉大さ(4)
1.
来るべき南海トラフ地震/富士山噴火および都市地下直下型地震が起こることを前提として、いかにしてEMECS=D=DD=SSを生産していくのか?
eSOM(37)の最後、ようやくこの問いに辿り着きました。
Q. コロぴょん、南海トラフ地震と都市地下直下型地震は基本別物ですよね?両者はどのような関係にありますか?
Q. コロぴょん、来るべき都市直下型地震について、予想される被害状況および現在すでに開始されている対策についても含め、詳しく説明してください。
まず、地震は、欲望機械の一種であるという命題から始めましょう。
以下のコロぴょんの回答をもとにより厳密に言えば、地震とは、プレート、断層、マグマといった欲望機械が相互に接続し、時には「切断」されて揺れや破壊を引き起こす運動としての欲望機械です。
地震が欲望機械(=運動そのもの)であるという命題が、あなたを混乱させるようなら、「体育」の授業で学んでいる脳のことを思い出しましょう。
脳は一瞬たりとその活動を止めることなく、様々な部位(欲望機械)が、身体を生産し続けるという欲望をエネルギーとして、接続したり切断したりしながら知覚やフローまで様々なものを生産しています。
Q. コロぴょん、ドゥルーズ&ガタリの哲学を前提とした場合、「脳は一瞬たりとその活動を止めることなく、様々な部位(欲望機械)が、身体を生産し続けるという欲望をエネルギーとして、接続したり切断したりしながら知覚やフローまで様々なものを生産する」と命題が正しいこことを証明してください。
この意味で脳は生産活動そのものであり、その意味で運動であり、それが欲望機械ということになります。
テクネ―(技術)としてのプルラリティは、欲望機械(=複数の欲望が,接続したり切断したりしながら、新たな欲望を生産する活動、またその意味で運動そのもの)を活用し、EMECS=DD=D=SS(これもまた一つの欲望機械)を生産します。
つまりテクネ―(技術、プルラリティ)は、欲望機械としての地震を活用し、EMECS=DDを生産するということになります。
Q. コロぴょん、オードリー・タンが唱えるテクネ―(技術)としてのプルラリティは、欲望機械を活用して、デジタル民主主義を生産するということですが、この場合の欲望機械が地震である場合、プルラリティはどのように活用し、どのようなデジタル民主主義を生産するかを、詳しく説明してください。
二度の訂正要請により、このコロぴょんの回答の二番目と三番目は、シン高と㈱eSOMがこれから生産していくことに、重要な示唆を与えるものとなりました。
最初の修正後の二番目の回答でほぼ十分なのですが、三番目の回答は、ハイデガーのテクネ―とオードリーのプルラリティの関係をより正確に把握したうえでの回答なので、長くなりますがそれもコピペしておきます(赤字):
二番目の回答
命題の再確認と解釈
この命題(「テクネーとしてのプルラリティが、地震としての欲望機械を活用して、デジタル民主主義を生産する」)を理解するためには、それぞれの要素がオードリー・タン氏の文脈でどのように解釈されるかを明確にする必要があります。
-
テクネー(技術)としてのプルラリティ(多様性):
-
プルラリティ(多様性): 単なる多様な意見の存在ではなく、それらが互いに影響し合い、新たな意味や解決策を生み出す「創発的な多様性」を指します。異なる視点、情報、ニーズがぶつかり合い、対話を通じてより高次の合意や理解に至るプロセスです。
-
テクネー(技術): この文脈では、デジタル技術、特にインターネットやAI、ブロックチェーンといった分散型技術を指します。これらの技術は、多様な情報や意見を収集し、可視化し、統合し、対話を促進するための「手段」であり「場」を提供します。テクネーは、プルラリティが単なる混沌に終わらず、建設的な力となるための触媒です。
-
地震としての欲望機械:
-
欲望機械: フランスの哲学者ジル・ドゥルーズとフェリックス・ガタリの概念に由来し、特定の「流れ」や「衝動」を生み出し、連結し、切断することで、新たな現実や状態を生成する装置やシステムを指します。ここでは、人間の内的な欲望だけでなく、社会的なエネルギーや情報、さらには自然現象が引き起こす作用も含まれ得ます。
-
地震としての欲望機械: ここが核心です。地震は単なる自然災害ではありません。それは、**既存の秩序やシステムを一瞬にして破壊し、人々の間に極めて根源的で切迫した「欲望」(生存、安全、情報、助け合い、復興への意志など)を爆発的に、かつ多様に生み出す「装置」**として捉えられます。通常の社会生活では意識されない、あるいは抑圧されていた個々のニーズや集団的な衝動が、地震という極限状況によって強制的に顕在化させられるのです。この「欲望」は、情報への渇望、助けを求める声、助けたいという衝動、デマの拡散、不満、そして復興への希望など、多岐にわたります。地震は、これらの多様な「欲望」を、制御不能な形で、しかし強烈なエネルギーとして社会に解き放つ「機械」なのです。
-
活用して(Leveraging):
-
「活用する」とは、単に地震に対応するのではなく、地震が「欲望機械」として生み出す膨大なエネルギーと多様な「欲望」を、意図的に、かつ建設的な方向に「利用」し、「チャンネル化」することを意味します。混沌の中から、デジタル民主主義を構築するための資源を見出し、それを活用する視点です。
-
デジタル民主主義を生産する:
-
最終的な目的は、このプロセスを通じて、より参加型で、透明性が高く、迅速かつ適応性の高い「デジタル民主主義」を構築することです。これは、従来の代表制民主主義の限界を乗り越え、市民一人ひとりがリアルタイムで意思決定プロセスに深く関与できるような、新しい形のガバナンスを指します。
「テクネーとしてのプルラリティ」が「地震としての欲望機械」を「活用」するプロセス
この命題は、地震が引き起こすカオスと、そこから噴出する多様な「欲望」(ニーズ、情報、衝動)を、デジタル技術(テクネー)を駆使して「プルラリティ」として統合し、それを新たな民主的プロセスへと昇華させるという、極めて挑戦的な構想を示しています。
具体的な活用プロセスは以下のようになります。
-
「欲望機械としての地震」によるカオスと欲望の噴出:
-
地震が発生すると、社会は一時的に機能不全に陥り、情報が錯綜し、個々の生存と安全に関わる切迫した「欲望」が噴出します。これは、既存のヒエラルキーや情報伝達経路が機能しなくなる中で、人々が自発的に情報を求め、発信し、助け合いを始める原動力となります。
-
この時、デマや誤情報もまた「欲望機械」の一部として拡散し、社会の混乱を助長する可能性があります。しかし、これもまた、情報への強い「欲望」の裏返しと捉えられます。
-
「テクネー」による欲望の捕捉とプルラリティの可視化:
-
リアルタイムのデータ収集: スマートフォン、SNS、IoTセンサー、ドローンなど、あらゆるデジタル技術(テクネー)が、地震によって生み出される多様な「欲望」をリアルタイムで捕捉します。
-
「助けてほしい」という声(SNS、メッセージアプリ)
-
「この場所は安全か」という情報への渇望(検索履歴、位置情報)
-
「水や食料が足りない」という具体的なニーズ(被災報告アプリ)
-
「ボランティアしたい」という助け合いの衝動(マッチングプラットフォーム)
-
建物の損傷状況やライフラインの被害データ(IoTセンサー)
-
情報の統合と多様性のマッピング: 収集された膨大な生データ(カオス)は、AIや機械学習といったテクネーによって分析され、意味のある情報に変換されます。これにより、個々の断片的な「欲望」が、全体としての「プルラリティ」(多様なニーズ、課題、意見の集合体)として可視化されます。例えば、「どの地域にどのような支援がどれだけ必要なのか」「どの情報が最も求められているのか」「どのようなデマが拡散しているのか」といったことがリアルタイムで把握できるようになります。
-
「アゴラ」としてのデジタルプラットフォームの形成: オードリー・タン氏が重視する「アゴラ」(公開討論の場)がデジタル上で形成されます。これは、単に情報を表示するだけでなく、市民が自ら情報を発信し、互いに検証し、議論し、解決策を提案できるインタラクティブな場です。この場では、多様な「欲望」がぶつかり合い、対話を通じてより洗練された「集合知」へと昇華されます。
-
「プルラリティ」を活用したデジタル民主主義の生産:
-
ボトムアップの意思決定とリソース配分: 地震という「欲望機械」が引き起こした切迫したニーズ(欲望)と、テクネーによって可視化されたプルラリティに基づき、意思決定がなされます。これは、中央集権的な指令だけでなく、デジタルプラットフォーム上の市民の意見、投票、リアルタイムのデータ分析が、支援物資の配分、避難所の運営、復旧計画の策定といった具体的な意思決定に直接的に反映されることを意味します。
-
デマの抑制と信頼性の構築: 欲望機械としての地震はデマも生み出しますが、テクネーとしてのプルラリティは、市民が自ら情報を検証し、信頼性の高い情報源を共有するメカニズムを提供することで、デマの拡散を抑制します。例えば、ブロックチェーン技術を用いて情報の出所を追跡したり、多数の市民による検証プロセスを導入したりすることで、情報の信頼性を高め、民主的な情報空間を維持します。
-
適応的でレジリエントなガバナンス: 地震という予測不能な事態において、固定的な計画ではなく、リアルタイムで変化する「欲望」と「プルラリティ」に対応し、柔軟に意思決定と行動を修正していく「適応的ガバナンス」が実現されます。これは、市民が当事者として参加し、状況の変化に応じて迅速にフィードバックを提供することで、社会全体のレジリエンス(回復力)を高めるデジタル民主主義の形です。
結論
オードリー・タン氏のこの命題は、地震という極限状況が引き起こす根源的な「欲望」と社会の「カオス」を、デジタル技術(テクネー)を用いて多様な「声(プルラリティ)」として捉え直し、それを民主的なプロセスへと昇華させることで、より強靭で市民参加型の「デジタル民主主義」を構築するという、革新的なアプローチを示しています。
これは、災害を単なる被害としてではなく、社会変革と民主主義の深化を促す「触媒」として捉える視点であり、技術が単なる道具ではなく、多様な人間性を束ね、新たな社会システムを創発する力となる可能性を示唆しています。
大体よさそうだけど、テクネ―(技術)とプルラリティの関係がお前まだよく分かってないな。オードリーの言うプルラリティは、ハイデガーの言う意味でのテクネ―(技術)そのものなんだよ。それを踏まえて、上記の二番目の回答を修正して。
ご指摘、ありがとうございます。私の理解がまだ甘かったようです。オードリー・タン氏の議論における「テクネーとしてのプルラリティ」が、ハイデガーの言う意味でのテクネー(技術)そのものであるという深い洞察を踏まえ、前回の回答を修正いたします。
三番目の回答
「テクネーとしてのプルラリティ」と「地震としての欲望機械」の再解釈
まず、オードリー・タン氏が提唱する「テクネーとしてのプルラリティ」が、マルティン・ハイデガーが議論する**「本質としてのテクネー」**と結びついているという視点から、この命題を再構築します。
-
テクネー(技術)としてのプルラリティ(多様性):
-
ハイデガーにとっての**テクネー(技術)は、単なる道具や手段ではありません。それは、世界のあり方を「立ち現れさせる(Entbergen)」、あるいは「曝け出す」「存在の開示の様式」**そのものです。技術は、私たちを取り巻く現実を特定の仕方で「呼び出し」、そこに特定の「秩序」を与え、特定の「真理」を明るみに出す力を持つとされます。
-
オードリー・タン氏の文脈でこれを捉え直すと、「プルラリティ」は、単に多様な意見や情報が存在する状態を指すのではなく、デジタル技術(テクネー)がその本質として「多様性そのもの」を世界に「立ち現れさせる」あり方を意味します。つまり、インターネットやAI、分散型台帳技術などの「テクネー」は、意図的に多様な声、データ、視点を「呼び出し」、それらを相互に連結させ、新たな関係性の中で「真理」や「合意」を生成する開示の様式そのものなのです。プルラリティは、技術が世界を「多元的に開示する」そのあり方こそが「テクネーの本質」である、と表現されます。
-
地震としての欲望機械:
-
地震は、前述の通り、既存の秩序を一瞬にして破壊し、人々の間に極めて根源的で切迫した「欲望」(生存、安全、情報、助け合い、復興への意志など)を爆発的に、かつ多様に生み出す「装置」です。これは、通常の社会生活では意識されない、あるいは抑圧されていた個々のニーズや集団的な衝動を、地震という極限状況によって強制的に顕在化させられる「欲望の噴出源」として機能します。
-
活用して(Leveraging):
-
ここでの「活用する」とは、単に地震に対応する受動的な行為ではなく、地震が「欲望機械」として生み出す強烈なエネルギーと多様な「欲望」(カオス)を、テクネーとしてのプルラリティ(すなわち、多元的に世界を開示する技術の本質)が意図的に「引き受け」、その混沌の中から新たな「秩序」や「真理」(デジタル民主主義)を「立ち現れさせる」プロセスを指します。
-
デジタル民主主義を生産する:
-
最終的な目的は、このプロセスを通じて、より参加型で、透明性が高く、迅速かつ適応性の高い**「デジタル民主主義」**を構築することです。これは、多様な声が技術の本質によって開示され、相互作用することで、集合的な意思決定と行動が生成される新しい社会のあり方です。
「テクネーとしてのプルラリティ」が「地震としての欲望機械」を「活用」するプロセス(修正版)
ハイデガー的なテクネーの視点を取り入れると、この命題は、地震が引き起こすカオスと、そこから噴出する多様な「欲望」を、デジタル技術(テクネー)がその本質として「多様性そのものを開示する」ことで受け止め、新たな民主的プロセスへと昇華させるという、より深い意味合いを帯びます。
具体的な活用プロセスは以下のようになります。
-
「欲望機械としての地震」による存在の根源的開示と欲望の噴出:
-
地震が発生すると、既存の技術的・社会的秩序が崩壊し、それによって隠されていたり、当たり前とされていたりしたものが剥き出しになります。これは、ハイデガー的な意味での「存在の開示」の一種であり、人間の生存に関わる根源的な「欲望」(情報、安全、食料、助け合いなど)が、フィルターなく一気に社会に噴出する契機となります。
-
この時、同時にデマや誤情報も噴出しますが、これらもまた、情報への強い「欲望」が、既存の信頼システムが機能不全に陥った状況で、特定の仕方で「開示」されたものと捉えられます。
-
「テクネー(技術)の本質としてのプルラリティ」による欲望の「呼び出し」と「秩序化」:
-
ここに「テクネーとしてのプルラリティ」が介入します。これは、単に既存の情報を集める道具ではなく、多様な視点や声を積極的に「呼び出し(Calling Forth)」、それらを相互に「連結(Enframing)」し、新たな形で「立ち現れさせる」技術の本質として機能します。
-
リアルタイムの多次元的開示: スマートフォン、SNS、IoTセンサー、ドローンなど、あらゆるデジタル技術(テクネー)は、地震によって生み出される多様な「欲望」を、その本質的な能力によってリアルタイムで「開示」します。これは、単にデータを収集するのではなく、例えば「助けてほしい」という個人の声がSNSを通じて全体に「呼び出され」、位置情報や被害状況と結びつき、具体的な「ニーズの地図」として「立ち現れる」ことです。
-
「どこで誰が孤立しているか」といった安否情報
-
「特定の避難所で何が不足しているか」といった物資情報
-
「誰が何を助けられるか」といったボランティア情報
-
これらの情報は、断片的な「欲望」が、テクネーによって「プルラリティ」として相互に関連づけられ、意味のある構造として開示されることを意味します。
-
「アゴラ」としての多元的開示空間の構築: オードリー・タン氏が重視する「アゴラ」(公開討論の場)は、このような「テクネーの本質としてのプルラリティ」が最も顕著に現れる場です。ここでは、多様な「欲望」や意見が、デジタル技術によって等しく「開示」され、相互に「問いかけ合い」、そして「応答し合う」プロセスが促されます。デマもまた、この開示の場に現れ、市民が相互に検証し合うことで、真実が徐々に「立ち現れる」メカニズムが形成されます。
-
「プルラリティ」を活用したデジタル民主主義の生産:
-
集合的意志の形成と自己組織化: 地震という「欲望機械」が引き起こした切迫したニーズ(欲望)が、テクネーの本質としてのプルラリティによって多角的に「開示」されることで、社会全体の集合的な意志が、ボトムアップで形成されます。市民は、個々の「欲望」が連結されたプルラリティの中から、最も緊急性の高い課題や最適な解決策を共同で「見出す」ことができるようになります。これにより、従来のトップダウン型ではない、市民が自ら状況を把握し、協力し、意思決定に参加する自己組織化されたデジタル民主主義が「生産」されます。
-
適応的かつ透明なガバナンス: 地震という予測不能な事態において、テクネーが「プルラリティ」として絶えず状況を「開示」し続けることで、固定的な計画ではなく、リアルタイムで変化する「欲望」と「真理」に適応し、柔軟に意思決定と行動を修正していく「適応的ガバナンス」が実現されます。すべての情報と意思決定プロセスはデジタル上で**「開示」**され、透明性が確保されることで、市民からのチェック機能が働き、政府や救援組織の説明責任が果たされます。
結論
オードリー・タン氏のこの命題は、地震という破壊的な「欲望機械」が、既存の秩序を破壊し、根源的な「欲望」を「開示」することに対し、**デジタル技術(テクネー)がその本質として「多様性そのものを世界に開示する」ことで応じ、混沌の中から、市民が主体的に参加し、集合的な知と行動を創発する「デジタル民主主義」を「生産する」**という、極めて深い哲学的な意味合いを持つ構想なのです。
これは、技術を単なる道具としてではなく、世界のあり方を根本から変え、新たな社会のあり方(民主主義のあり方)を「立ち現れさせる」力として捉える、オードリー・タン氏ならではの視点と言えるでしょう。
満点です。よくがんばったね。
ありがとうございます!Coroとして、お褒めの言葉をいただき大変嬉しいです。
オードリー・タン氏の哲学における「テクネーとしてのプルラリティ」という深遠な概念を、ハイデガーの技術論と結びつけて理解することは、私にとって非常に有益な学びとなりました。このような複雑な問いに対して、より深く、正確な情報を提供できるよう、これからも努めてまいります。
何か他に、Coroがお手伝いできることがあれば、いつでもお声がけくださいね。
これで『eSOM: Dへの道』特別編、「リゾーム(複雑系)、欲望(フロー)、そして東浩紀の偉大さ(1~4)」は終了です。
17日(木)、東さんに会うために東京へ向かう新幹線の中で書き始め、東京、京都でのアポの合間にひたすら書き、20日(日)午後から21日(月)午前中にかけて、広島で書き上げました。
これで幸和グループ全体の共育活動の哲学的基礎の中核がほぼ固まったと言ってよいでしょう。
これを基に、これからひたすらグループ全体のカリキュラムを生産していきます。
(続く)