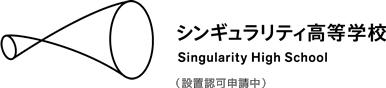eSOM (イゾーム)
eSOM (イゾーム)
Dへの道、あるいはシン高と幸和の物語
eSOM: Dへの道(37) リゾーム(複雑系)、欲望(フロー)、そして東浩紀の偉大さ(3)
1.
『eSOM』(36)では、プルラリティが、田辺元の「種の論理」に似た、D=DD=SS=EMECSのためのテクネ―≒アルゴリズムであることを見ました。
「リゾーム(複雑系)、欲望(フロー)、そして東浩紀の偉大さ」の三回目にあたる今回はついに、「種の論理」とプルラリティの「微妙な差異」について論じます。
つまり、GEACS(大東亜協栄圏=ファシズム)とEMECS(D=DD=SS)、さらには弁証法とイゾームの「微妙な差異」について。
それを論じる中で、「東浩紀の偉大さ」が浮き彫りになることでしょう。
前回、田辺もオードリーも、目標(絶対善DD=D=SS=EMECS)達成にむけて、テクネ―≒アルゴリズム(「種の論理」ないしプルラリティ)を通して、種ないしリゾームを活用する点においては同じであることを見ました。
また、絶対無=eSOM(例:オードリーの山寺)の立場に身を置き、その立場から究極目標=絶対善=光(類ないしD=DD=SS)と、その生成に必要なテクネ―を受け取り、究極目標に向けての「命懸けの飛躍」(柄谷)を行うという点においても同じでした。
GEACSとEMECSは、そこまで同じでありながら、どこで袂を分かつのでしょうか?
東さんの論を至極簡単に言えば、絶対善(DD=D=SS=EMECS)の内容が、一人の特別な存在(単一者、王、神)による「単一な声」として与えられるか否かによって、広域経済文化圏はGEACSにもなれば、EMECSにもなります。
ここで重要なのは、人々はその「声」に嫌々従っているのではなく、自らその「単一の声」に従うことを欲しているということです。
つまり、「単一の声」に従うことが、自らの欲望(フロー)の対象であるということです。
多くの人々が、みずから進んでGEACS構築のために、その構築を阻害する敵(であると「単一の声」が名指す者)を殺し、また自らも、その構築のために死んでいったのです。
勿論、異議を唱える人々も大勢いました。
しかし当時の民主制では、より多くの人々が「単一の声」に従うことを欲しているとされ、「民主的に」国内外の殺戮が正当化されました。
(従って、民主主義なら何でもよいというわけではなく、どのようなシステム(テクネ―)で民主主義を実行するかが問題となるわけです。)
2
ではなぜ、それほど多くの人々にとってのフロー(欲望)の対象が、「天皇の声」であったのでしょうか?
言うまでもなくそれには、フロー(欲望)を活用してGEACSを構築するためのテクネ―によるものでした。
その最たるものが、教育、メディア(ラジオ、新聞)、そしてエンタメ(大衆小説、映画)を通して広められる、「日本イデオロギー(=ファシスト・イデオロギー)」としての「国史(=国民の歴史)」であったというのが、私の最後の論文である「A Secret History」その他の研究論文(全て英語)の主旨でした。
そして、国民の歴史(=ファシズム・イデオロギー)を人々に届ける媒体として最も威力を発揮したのが、シン高のバイブルである『バガボンド』の原作ということになっている吉川英治の『宮本武蔵』でした。
ここで、『宮本武蔵』の内容を知っている人は訝しがることでしょう?
「あの小説に天皇とか日本とか出てきたっけ?」と。
人々の欲望(フロー)を活用して国家(B)を構築するための技術(テクネ―)としての国史=ファシズム・イデオロギーにおいて最も重要なことは、前回のゼミで少しお話した「否定神学」を、物語のプロットとして持つということです。
既存の社会(=種)の中で、(主観的ないし客観的に)虐げられている人々に対し、「嘗てこの国は、現在のような問題が存在しない楽園(=類)であった、私がそれを現前せしめ、あなた方虐げられた民をそこに連れていく」という物語(=声)のプロットが、否定神学の基本です。
この国史のプロットを、当時の日本社会で最も虐げられていた人々である農村の若者に最も魅力ある形で届け、彼らが自発的に戦場に向かい、殺戮を行うことに貢献したのが、吉川英治の『宮本武蔵』だったわけです。
そうしたことから、『宮本武蔵』のどの辺りが、GEACSおよび戦争遂行のためのテクネ―として機能したのかという問いは、是非いつか、国語かなんかの授業の課題にしたいですね。
ここで重要なことは、国家によって作られたわけではなく、一見、政治とは無関係そうなエンタメ作品が、「天皇の声」として機能し、人々のフロー(欲望)を生産していくということです。
現在、日本のエンタメが世界的な人気を博していることから政財界(B、C)は、数少ない日本の成長産業としてエンタメ産業(コンテンツ産業)に注目しています。
つまり前回の戦争の時と同じように、コンテンツ産業(エンタメ産業)という戦争機械を捕捉しようとしています。(前回の戦争の場合は特に、当時、大衆に浸透しだした映画の成長に日本ファシスト国家は注力しました。)
現在放映中のNHK大河ドラマ『べらぼう』が、そのためのテクネ―(技術)であることは言うまでもないでしょう。
Q. コロぴょん、ドゥルーズ&ガタリの「戦争機械」と言う概念を、その「捕捉」、「脱領土化」の意味と共に、「リゾーム」に関連づけながら詳しく説明してください。
Q. コロぴょん、上記の君の戦争機械とリゾームの関係の説明に従うと、戦争機械はリゾームの一形態であり、したがってまた、戦争機械は欲望機械の一種ということになりますよね?
Q. コロぴょん、国家によって捕捉された戦争機械は、国家装置化すると考えて差し支えないですか?例えば、国を担う人々に軽視されがちであった大衆小説の代表作『宮本武蔵』が、農民を兵士として戦争に駆り出すために役立つということで大衆文学が国に認められるようになることなどは、戦争機械の国家イデオロギー装置化と言ってよいのでしょうか?
Q. ドゥルーズ&ガタリと「脱領土化」と、デリダの「脱構築」の接点を、東浩紀の「郵便的脱構築」および「誤配システム」を踏まえたうえで、詳しく論じてください。
こうしたことから東さんは、サブカルチャーを論じることを自身の仕事の中心の一つに据えられてこられたのだと思います。
国家に捕捉され、国家イデオロギー装置化が進行している欲望機械/リゾーム(例:戦争機械)を、脱領土化(≒誤配システムによる郵便的脱構築)することが、東さんの実践活動であると私は理解しています。
そんな東さんの言論を「導きの糸」としながらシン高およびその姉妹組織である㈱eSOM(イゾームと読みます)も、EMECS=D=DD=SSの生成を促すコンテンツ産業の成長に貢献する人間を育成するプログラムを開発していきたいと考えています。
3
「天皇の声(一元的な声)」の郵便的脱構築(≒脱領土化)という問いを、『宮本武蔵』と『バガボンド』を例にとって探究することは、『バガボンド』をバイブルとする我々シン高には最適でしょう。
私と同じ歳で、熊本大学哲学科中退である井上雄彦は、最も効果的な(捕捉された)戦争機械であった『宮本武蔵』を、脱領土化(≒脱構築)していると私が考えています。
国家に捕捉され、国家イデオロギー装置と化した「戦争機械」(=国家イデオロギー装置)である吉川英治の『宮本武蔵』が、半世紀以上の時を経て、井上とシン高に届けられ、我々を通して新たな欲望(フロー)と接続することで、新しいもの(EMECS構築のためのバイブル)として再構築(生成変化)されることこそ、誤配(郵便的脱構築)であり、かつ、脱領土化であると言えるのではないでしょうか。
言うまでもなくこの『宮本武蔵』というテキストの脱構築は、EMECSそのものが、我々のもとに誤配されたGEACSそのもの、その郵便的脱構築であることと連動しています。
となると『バガボンド』は、吉川の『宮本武蔵』として表現された天皇(およびそのメタファー)が発する「国史=ファシズム・イデオロギー=日本イデオロギー」から、「多様な声」としてのテクネ―(プルラリティ)への脱構築の表現でなければなりません。
では、『バガボンド』のどのあたりが、『宮本武蔵』の誤配(郵便的脱構築)として読めるのでしょうか?
(科学)技術に秀でた敵国・米国のメタファーである宿敵・小次郎が、マイノリティ(聾唖者)であり、武蔵(バガボンド)と唯一心が通じ合う親友、かつ、お手本(師)として描かれている点。
絶対善としての「天」が、弁証法的(階層的)に、垂直(上向)にあるのではなく、農民と接続し、武蔵(バガボンド)を含めた村民(欲望機械)が大地/地球(欲望機械)と接続し、生の糧である米(欲望機械)と接続するという生産活動そのものに求められている点。
(こうした、全て存在が、多様な欲望が接続したり切断したりすること(=生産活動)自体としての欲望機械であることを理解するための最適な表現は、『マトリックス』一作目のエンディングで、ミスター・アンダーソンからネオへと覚醒した主人公(キアヌ・リーブス)の目に映る、緑色に発光する記号の絶え間ない流れ(=エージェントやアパートの廊下などの全ての存在)であると言えるのではないでしょうか。
Q コロぴょん、ドュルーズ&ガタリ的に言えば、有機体であろうがなかろうが、全ての存在は欲望で出来ているということになるのでしょうか?
上記の、農業と関係した二つ目の誤配は、我々にとって特に重要です。
まず、これらドュルーズ&ガタリの主要概念を最も良く表現した芸術作品があります。
ベネッセアートサイト直島で展示されている《Ring of Fire – ヤンの太陽&ウィーラセタンの月》です:
同作品の批評は、いずれじっくり行うとして、ここでは、EMECS生産(今後は構築の代りに生産という言葉を使います)において最優先されるべき南海トラフ地震の対策と関連して、地震を通してドゥルーズ&ガタリの哲学理論の理解を深め、それを基にしたEMECS生産のためのプログラムを作成していきたいと思います。
(続く)