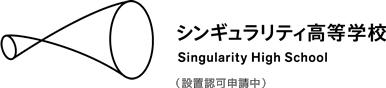eSOM (イゾーム)
eSOM (イゾーム)
Dへの道、あるいはシン高と幸和の物語
eSOM: Dへの道(36) リゾーム(複雑系)、欲望(フロー)、そして東浩紀の偉大さ(2)
1
さてさて、『プルラリティ』を分かり易くするため『eSOM: Dへの道』(35)は、一層混乱させてしまったかもしれません(笑)
そこで、「解説の解説」としてこの『eSOM(36)』を書くことにしました。
このところ立て続けに東京で東浩紀さんとお話させていただく機会がありました。
今週木曜にまたお会いする機会があるでしょう。
ゲンロンカフェのイベントや彼との会話の中で東さんは、eSOM (35) の内容を、誰にでも分かる形で説明するためのヒントを与えてくれました。
20世紀後半から現在に至るまでの思想で最も難解だと言われている概念の一つであるリゾームを、誰もが興味を持てる形で話せるところが、東さんが国内外の第一線の思想家と比べても突出している証拠です。
東さんの話を基にすれば、リゾーム(≒複雑系≒多様性)とは、「都心の雑居ビルで起きている様々な出来事」のようなものです。
みなさんは、「都心の雑居ビル」のイメージが沸きますかね?
東さんが好んで度々話す雑居ビルの説明とは、「入口にガードマンなどおらず、24時間色々な人が出入り出来て、比較的安価な家賃で借りれる一つ一つのオフィスで多種多様な人達が、怪しい事から訳の分からない事まで、本当に多様なことを行っている自由な空間」ということです。
一つひとつのオフィス(≒「集合的組織」by ハナ・アーレント)では、「好きなこと=フロー=欲望」を同じくする人が集まり、東さんのゲンロンカフェのような現代最高の知性による討論会や、地下アイドルとその「推し人」で構成されるライブが隣通しで行われていたりします。
そう、少し乱暴すぎるかもしれませんが、欲望≒フロー(時間を忘れて没頭出来る状態を欲すること)と考えることにしましょう。
そうすると、一つ一つのオフィスは、ドゥルーズ&ガタリの言う「欲望機械」と言えるかもしれません。
2
いずれにせよ、そんな雑居ビルの中で、例えば「ゲンロンカフェ」での討論会にやって来る至極優秀な若者は、トイレ休憩の時間に、夜中の2時過ぎに勝手にビルの女子トイレに入って来て、そこで無茶苦茶着飾って化粧もばっちり決めて、またどこかへ向かう女性の集団に出会い、なんだったらそのうちの一人と恋に落ちてしまう。
そしてそのファンキーな恋人がアニヲタであったがゆえ、現代思想にしか興味がなかったこの青年は、現代思想と取り入れた全く新しいアニメを世に送り出す。
恋人のアニメに対する欲望(フロー)の一部と、青年の現代思想に対する欲望(フロー)の一部がそれぞれ切断され、それら部分部分が接続することで新しい文化が創造/生成される。
こうした欲望/フローの切断/接続/生成変化という一連の運動が、リゾームということになるでしょう。
そんなふうに、様々な欲望=フローが、接続ー切断ー接続…を絶え間なく繰り返しているうちに、くだらないものから世界を変えるものまで生成されていく。
それが雑居ビルであり、そしてそれが「欲望=フローの網の目」としてのリゾームと考えてよいのではないかと思います。
東さんは、「チームみらい」党首の安野たかひろさんに、「チームみらい」はまず、雑居ビルに部屋を借りることから始めたほうがいい」と本気で提言していました。
その後、東さんは、「チームみらいは、中学から開成でそのまま東大入ったような連中ばかりで経験値が低すぎる、だから雑居ビルに部屋を借りて、色々な人間と交わることから始めたほうがいい」といったようなことをおっしゃっていました。
また東さんは、「自分も似たようなものだが(筑波大付属→東大)だが、株式会社ゲンロンを創業し、運営してきた経験が大きい」とも言っていました。
この東さんの言葉は、シン高の共育にとっても、EMECS(東地中海経済・文化圏)としてD=DD=SSを構築していくうえでも非常に重要です。
3.
EMECSとしてのD=DD=SSは、テクネ―(プルラリティ)によって同地域のリゾーム(=欲望(フロー)の運動)を活用して生成させていかなければなりません。
私が東さんに直接会って話したのは最近のことですが、私はEMECS=D=DD=SS=リゾーム(=欲望(フロー)の運動体)の構築を、大学院に入った1994年から構想しており、その当初から東さんの著作は私の「導きの糸」でした。
東さん本人にも伝えましたが、EMECS=D=DD=SSは「大東亜協栄圏」の脱構築(リミックス)です。
みなさんは、「大東亜協栄圏」をご存じですか?
一言で言えば、太平洋戦争を招いた、大日本帝国によるグローバル・ファシズムです。(資本主義と同じでファシズムも、「いつも、すでにグローバル」なのですが、それは今は触れないことにしましょう)
私の研究対象は、その「大東亜協栄圏(=グローバル・ファシズム)」の哲学的基礎を築いたと言われる田辺元(はじめ)が打ち立てた、「種の論理」という哲学理論でした。
田辺の「種の論理」がどのぐらい優れているかと言うと、我らがオードリー・タンらの著作『プルラリティ』の主張のかなりの部分が、「種の論理」に先取りされています。
ここで重要なのは、「かなりの部分」であって、「全部」ではないということです。
「種の論理」と「プルラリティ」のこの微妙な差異によって「Dへの道」は、最後の最後に、ファシズム=GEACS(Greater East Asian Co-Prosperity Sphere、大東亜協栄圏)とD=DD=SS=EMECSという真反対の方向へと、袂を分かつことになります。
GEACSとEMECSを分かつ「微妙な差異」とは何か?
どうすれば、「Dへの道」を、GEACSではなくEMECSに向かわせることが出来るのか?
四半世紀に渡って私に、この問いの解答に辿り着くための「導きの糸」を与え続けてくれているのが、東さんというわけです。
4.
東さんが与え続けてくれる「導きの糸」とは何かを説明するために、GEACS構築のための哲学である田辺の「種の論理」から始めることにしましょう。
そうすることにより、「種の論理」と「プルラリティ」の(つまり、GEACSとEMECSの)「微妙な差異」が浮き彫りにされるはずです。
まず大事なのは、「種の論理」における「種」とは、リゾーム(≒複雑系)に準ずるものであるということです。
実際に田辺は、「種」とは欲望であり、多様体であり、複雑系であると述べています。(元々、田辺は東大理学部で数学者を志していました。)
そして彼の「種の論理」という哲学理論は、理性によって制御不能な「種=欲望(フロー)の運動体」を「絶対善(D=DD=SSに準ずるもの)」の生成のために活用する技術(テクネ―)と見做すことが出来ます。
Q. コロぴょん、田辺元の「種の論理」はテクネ―としての技術(テクノロジー)の一種であると思われますが、それがどういうことかを詳しく論じてください。
では、「種の論理」は「テクネ―(技術)」として、どのように絶対善(=D=DD=SS)の構築のために種(=リゾーム=欲望の運動体)を活用することを可能にするのでしょうか?
この問いには、私が『eSOM』(21~22)で説いた『Good Enough Ancestor』を具体例として答える事が出来ます。
オードリーは、ある一つの「種/欲望(伝統的な社会)」と、それとは別なもう一つ「種/欲望(デジタル社会)」の対立によって生じた「裂け目(余白=絶対無)」に、「光(類=絶対善=DD/D/SS/EMECS)」が、その光を現実にするためのテクネ―(技術=プルラリティ=霊的な力)とともに「向こう側からやって来る」ことを直観します。
オードリーがこの直観を、種(伝統的な台湾社会)と種(デジタル社会)の対立から仏教の山寺へと身(個)を遠ざけ、そこで受け取ったことがとても重要です。
Q. コロぴょん、田辺元の「種の論理」における絶対善と絶対無のそれぞれの役割を、詳しく説明してください。
このように、「個(オードリー本人)」、「種(リゾーム)」、「絶対無(余白、裂け目)」、「絶対善(DD=D=SS=EMECS)」から構成される運動の論理が「種の論理」ということになります。
ここで重要なのは、「絶対善(DD=D=SS=EMECS)」は「(種に対する)類=絶対不可能性」とも呼ばれ、ジャック・ラカンの「現実界(Real)」にも比する、「言葉やイメージでは捉えきれない、名付けることが不可能な「生の現実」や「不可能なもの全体」」であるということが重要です。
また「Real(現実界)=絶対善=類=絶対不可能性」は、「私たちが普段「現実」と認識しているものとは異なる、より根源的で把握しがたい領域」」と言うことも出来るでしょう。
「種の論理」はこの「類」を中心に(まさに「中心に」)、次のように「類=D=DD=SS=EMECS」の構築をプログラムします(その意味で「種の論理」=テクネ―はアルゴリズム(問題解決の手順)と言えるかもしれません。)
①「現実界」としての「絶対善(DD=D=SS=EMECS)は、決して完全には(一般的な意味での)現実にはならない。
②しかしそれでも、それを(一般的な意味での)現実として構築しようとする(「命懸けの飛躍」)。
③そうすることにおいてのみ、(一般的な意味での)現実を、そこに潜む問題と併せて客観的/科学的/批判的に把握することが出来る。
④その上で、その問題の全てを解決することは出来ないまでも、ある程度は解決することが出来、結果、ある程度までは絶対善=類(D=DD=SS=EMECS)に近づくことが出来る。
⑤絶対不可能性として絶対善=類(D=DD=SS=EMECS)を構築するということは、このプログラムを繰り返すことに他ならない。
これは弁証法であり、かつ、LSP(レゴ・シリアス・プレイ)でもあるわけですが、その点に関してはいずれ詳しく論じることにしましょう。(その意味で、LSPもまた、テクネ―であるということが出来ます。)
また、この弁証法的運動が、スラヴォイ・ジジェクのイデオロギー論の概要ということになり、そのことは我々にEMECS構築の方法論上の深刻な問題を突きつけることになります(ちなみにジジェクのイデオロギー論においては、「vortex(渦)」がリゾームに該当します)。
Q. コロぴょん、「想像界(Imaginary)」、「象徴界(Symbolic)」、「現実界(Real)」から構成されるジャック・ラカンの精神分析の、それら三つの概念それぞれと、それら三つの概念がどのように関連し合ってラカンの理論を構成しているか、また、そうしたラカンの理論が、田辺元の「種の理論」や、スラヴォイ・ジジェクの『イデオロギーの崇高な対象』におけるイデオロギー論とどのような点で共通しているかを、詳しく説明してください。