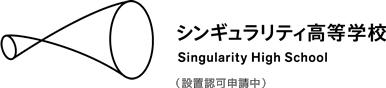eSOM (イゾーム)
eSOM (イゾーム)
Dへの道、あるいはシン高と幸和の物語
(小説)Xへの道、あるいはシン高物語(29):バガボンド、べらぼう、攻殻機動隊、そしてダンダダン
1.NHKスペシャル「新ジャポニズム」
14歳の君へ、そしてシン高のみんなへ
普段僕は全くテレビを観ない。
だから家にテレビがない。
見るのは、盆と正月に会津の実家に帰省し、母と居間にいる時だけだ。
この正月の帰省の際、テレビでは「新ジャポニズム」と題されたNHKスペシャルが放映されていた。
同番組により、世界中の若者が『進撃の巨人』や『ONE PEACE』をきっかけとして「X(=X(=見知らぬ人と見返りの関係にならずに交換するパターンである、柄谷行人さんの言う交換様式Dが支配的となる社会)」の構築へと向かっていることを知った。
その典型が、漫画家を志すジンバブエの31歳の青年ビル・マスグさん。
ビルさんは、『ONE PEACE』のあるシーンに「救われた」という。
(ナレーション)
「麦わらの一味であるニコ・ロビン。自分は生きることを望んではいけないと思っていた彼女が、ルフィの[「「生きたい」と言えェ!!!!」という]叫びを受け、[「生きたいっ!!!!」と]本音を吐き出すシーンだ。」
(ビルさんの発言)
「「イキタイ」。その言葉をよく覚えてる。涙が止まらなくなったことも。しばらく読み進められなかった。ぐっときすぎて。」
なぜこのシーンが、ここまでビルさんのハートに刺さったのか?
それは、この場面に初めて出会った当時のジンバブエの状況と関係している。
(ナレーション)
「ビルさんが『ONE PEACE』を読み始めた2008年頃、ジンバブエはハイパーインフレーションに陥っており、人々は自分が生きることに精一杯だった。そんな時、仲間を思うあのシーンが心に浮かんだという。」
(ビルさんの発言)
「もし近所に何か必要な人がいたら、近隣の住人は見返りを求めず貸す。「これは貸しだから」などとは決して言わない。[ハイパーインフレ当時のジンバブエでは]みんな同じ「舟」に乗っていた。アメリカの文化はより個人[主義]的な「私が私が私が、 私に私に私に」だ。でも日本は[集団主義的で]みんなで助け合う。」
相変わらず大手メディアの翻訳が最悪なので、ビルさん本人の発言を元に注釈・校訂を施した。
ちなみに大手メディアによる翻訳を通した情報操作は、日本だけに限ったことではない。
1990年、当時、米国の大学に通っていた僕は、アラビア語と日本語のバイリンガルのイラク人の友人と一緒に、湾岸戦争に関するCNNのニュースを観ていた(彼は幼い頃、家族と一緒にイラクから日本に逃げて来た)。
戦地で暮らす老女のインタビュー中、普段温厚な彼が声を荒げて言った。
「おばあさんは、「米国が私の国[イラク]を無茶苦茶にしている」と避難しているのに、翻訳では「米国が来てくれてほんと嬉しい、感謝している」と全くの出鱈目になっている!」と。
ビルさんの発言の翻訳はそこまで酷くないので、それをもとに、「(シン高および幸和グループの)メンバー」(以下、「メンバー」)が知っておくべき大事なことをここで確認しておこう。
そもそも米国をアメリカと呼んでいる時点で、NHKもビルさんも、知らないうちに米国のイデオロギーに自覚することなく取り込まれている。
かくいう私も北米にいる間、米国人以外の「アメリカ人(カナダ人、ラテンアメリカ人)」から指摘されるまで同じ過ちを犯していた。
米国をアメリカと呼ぶことに問題を感じていない時点で、米国の覇権主義、帝国主義に対するクリティカル・シンキングが欠けている、と。
上記のビルさんの発言を通して、「メンバー」が知っておかなければならないことがもう一つある(否、二つ、か)。
ビルさんは「American culture(米国文化)」、「Japanese culture(日本文化)」という言葉を、世界中の多くの人々同様、当たり前のように使っている。
しかしそうすることは、そうした「国民文化」の概念が、近代国民国家の構築のために作られたものであるという「歴史性」に無自覚であることの証左だ。
ちなみに「メンバー」には、「歴史性とは?」とか、「歴史性と歴史の違いとは?」とか、知らないことがあったら即座にAIに尋ねる習慣を身に着けて欲しい。
Q. コロちゃん、「歴史」と「歴史性」の概念上の違いは?
こうした問いが生まれたら、出来れば「物事の歴史性に無自覚であることの弊害は?」といった問いまで自発的に立てて、AIに尋ねれるようにまでなって欲しい。
Q. コロちゃん、物事の歴史性(歴史ではなく)に無自覚であることの弊害は?
AI の時代に「○○なんて知らない」とかいう言葉を発することは、人間としてご法度である(少なくとも「メンバー」においては)。
2.「文化」としての「交換様式A/D」
一言で言え、ビルさんがハイパーインフレ下のジンバブエで見たものが、「互酬(贈与と返礼)」としての「交換様式A(知り合いと見返りの関係にならずに交換するパターン)」と言える。
この交換様式が世界中で支配的になった時、それは交換様式D(以後、「D」)と言われる。
そして我々「メンバー」は、「D」が支配的となった社会/世界を「X」(「」付きの)と呼ぶ。
柄谷さんは「D」への、つまりは「X」への方向性を示した。
その方向性を基に「メンバー」は、柄谷さんと共にそれを構築していく。
一方、そうした「交換様式A/D」に対して、ビルさんが「アメリカ文化」と呼ぶものが、実のところは「商品交換」としての「交換様式C(見知らぬ人と見返りの関係になって交換するパターン)」だ。
いわゆる「資本主義」における交換様式だ。
ここで「資本と資本主義といった概念の定義はそれぞれどのようなもので、互いにどのように関係するの?」、「カール・マルクスにおけるそれらの概念と、近代経済学における同概念の違いは?」(最初の問いの答えで、AIがこの違いに触れてくれる)、「柄谷行人の交換様式Cと、カール・マルクスにおける資本および資本主義といった概念との関係は?」などの問いを立てれてAIに尋ねれれる時点で、何等かの科目(例:社会)の単位取得のためのレポートは満点だ(僕がファシリテーターなら)。
Q. コロちゃん、柄谷行人さんの「交換様式論」が依拠するカール・マルクスにおける「資本」、「資本主義」といった概念をそれぞれ定義して、それらの関係を教えてください。
Q. コロちゃん、柄谷さんの交換様式論における交換様式Cと、カール・マルクスの資本、資本主義といった概念の関係を教えてください。
3.「A/D」と、「B」や「C」とのややこしい関係
ビルさんは、ハイパーインフレーション下のジンバブエにあったという「A」は、「日本文化」という国民文化に通じるという。
これも「当たらずも遠からず」だ(その逆もまた真)。
まず歴史性との関係で上記で触れたように、「日本文化」や「米国文化」といった国民文化は全て、国家と国民の間に顕著な、「略取と再分配」としての「交換様式B(知り合いと見返りの関係になって交換するパターン)」の「略取」の部分から国民の目そらすか、それを「良きもの」と誤認させる「装置(ないし道具)」に過ぎない。
いまだに多くの日本の幼稚園から高校までに巣食う、「日本文化」としての「集団主義」と、それを身体に刻み込ませるための「躾け、教育」などがその典型と言えるだろう。
それが、近代以前は社会階層的にも地域的にも部分的でしかなかった「騎士道精神」や「武士道」を、近代以降、「国民文化」として再構築し、本質的に「戦争機械」である近代国民国家による戦争およびそのための教育に利用されてきた。
その解明が、ミシェル・フーコーを筆頭に、柄谷行人(『日本近代文学の起源』の頃の)、エドワード・サイード、ベネディクト・アンダーソンといった理論家たちによる、20世紀後半の最大の人文・社会科学の成果と言ってよいだろう。
一般に彼らの理論的立場は「社会構築主義」と言われるが、シーモア・パパートによる教育学上の「構築主義」と一線を画すべきである。
ただ、パパートの師であるジャン・ピアジェ(「構成主義」を唱えた)と、フーコーとともに20世紀後半の思想界を牽引したジャック・デリダ(「脱構築」を唱えた)の関係を考えると、これら二つの「構築主義」は全くの別物と考えるべきではない。
フーコー等の社会構築主義、パパートの構築主義、そしてデリダの脱構築はどれも、「グループ」にとって最も大切な理論であるため、それらの関係については後日詳解することになるだろう。
4.「いき」+「交換様式論」+「脱構築」=「 リミックス(re-mix)」
では、2008年当時のハイパーインフレ下のジンバブエでビルさんが目撃した「A」を、「日本文化」の内に見るビルさんは完全に誤りなのか?
決してそうではない。
思想史家最後の仕事として僕は、九鬼周蔵先生が著わした世界的な名著『「いき」の構造』で彼が論じた「いき」こそが、(少なくとも一つの)「A」であることを論ずる論文を残し大学を去った。
思想史家としての最後の論文「A Secret History: Tosaka Jun and the Kyoto Schools」はこちら:
↓
この論文で僕は、「いき」には、日本という近代国民国家による民からの「略取」に対し、被略取者の民自身を盲目にし、民を「国民」として戦争へと動員するための装置である「日本文化(=日本イデオロギー)」としての「いき」と、僕が「バガボンディズム(Vagabondism)」と名付けた、「A」としての「いき」の両面があることを論じた。
一般に、近代国民国家・日本の「国民文化」と見做される(「Bの文化」としての)「いき」から、それが抑圧する側面(この場合は「Aの文化(=バガボンディズム)」)を抽出すること。
簡単に言えばそれがデリダの言う「脱構築」だ(と僕は考える)。
そして論文は、「「A」の文化」としての「いき(=バガボンディズム)」が、「東軍」と「西軍」の対立を止揚する力となる時、それは「「D」の文化」、つまりは「「X」の文化」となったと言われることを論じた。
枚数の関係で、論文では柄谷さんの交換様式論には絡ませていないが、要はそういうことだ。
論文では、こうした柄谷さんの「交換様式論」と融合した脱構築を「リミックス(re-mix)」と呼んだ。
これからもそうする。
僕は、デリダと柄谷さんの関係は、井上雄彦の漫画『バガボンド』における小次郎と武蔵のようだと思っている(なぜ急にこの漫画の話になるかは、この後すぐ)。
『私の謎』(朝日新聞に連載中の柄谷さんの連続インタビュー)のデリダとの親交を語った回を読んで、その思いを新たにした。
僕はなぜか、柄谷さんをはじめ、デリダととても親しかった人々から直接学ぶ機会が多かった。
言ってみれば「孫弟子」のようなものだ。
そんな私がこうして、彼の「脱構築」と柄谷さんの「交換様式論」をミックスすることで、「X」を構築しようとしている。
きっとデリダもあの世で喜んでくれているだろう。
5. 『バガボンド』
なぜ「A/D」をバガボンディズムと名付けたのか?
『「いき」の構造』の英訳版で、「粋人」がvagabond(放浪者、漂流者、さすらい人の意)と訳されている。
しかしそれだけが理由ではない。
井上雄彦の漫画『バガボンド』の主人公である宮本武蔵(=バガボンド)に、「いき」の最高表現を見たからだ。
特に井上が墨で描くその姿そのものに。
2009年、久々にニューヨーク・シティ(NYC)を訪れた時のことだ。
長年、私にとっての情報の発信源であった紀伊国屋に足を運んだ。
エスカレーターが二階にさしかかると、壁一面に描かれた武蔵の姿が目に飛び込んできた。
その瞬間に私は、この物語の中の武蔵(以後、「武蔵」)に同化した。
それぐらい自分を「武蔵」に投影してきた。
大学を辞して日本に戻ってからしばらくの間、ある農業法人で田んぼを作っていたことも、この同化と無縁ではないはずだ。
物語は、「武蔵」が剣を置き、田んぼを作る第37巻で井上の筆が止まっている。
当然だ。
「X」(=「D」が支配的となる社会/世界)は、そうそう簡単に描けるものではない。
僕と同じ歳の井上は、熊本大学文学部哲学科中退だ。
僕と同じ歳で哲学に興味があって、柄谷行人から影響を受けていないはずがない(と勝手に思っている)。
それほど彼が描く「武蔵」の物語は、我々の『Xへの道、あるいはシン高物語』とシンクロする。
巷の噂では、井上はそろそろ連載を再開するらしい。
これまた4月に開校する我々と時を同じくする。
「メンバー」は皆「武蔵(=バガボンド)」となり、井上と一緒に「Xへの道」をゆく。
6.『夢酔独言』
そもそも井上の『バガボンド』は、吉川英治の『宮本武蔵』(1935~1939)の「リミックス」だ。
吉川版は、その『朝日新聞』での連載時期からも察しがつくように、中国と米国との戦争への機運を高めることを意図して書かれた生粋の「日本イデオロギー」だ(また、このことから、戦時中の『朝日新聞』がどのような新聞であったかが窺い知れる)。
それを「戦争への道」ではなく「Xへの道」をゆくストーリーに「リミックス」するという点では、構築された意味としては、これまた、生粋の「日本イデオロギー」である『「いき」の構造』(1935年)を「リミックス」し、「バガボンディズム=A/Dの文化」として再構築しようとしている我々と同じだ(九鬼先生は吉川のように、直接的に戦意高揚のために書いたわけではないが)。
そもそも我々の『Xへの道、あるいはシン高物語』自体が、僕が15歳(1983年)の時に司馬遼太郎の『竜馬がゆく』を読んて以来、この戦後版「日本イデオロギー」のリミックスとして構築されている(この小説がいかなる意味で戦争イデオロギーとしての「(戦後版)日本イデオロギー」であるかについては、いずれ詳解する)。
この司馬の物語で重要な役割を担う勝海舟の父である勝小吉(1802-1850)が著わした『夢酔独言』(1843)が、私の人生を決定付けたと言っても過言ではない。
1991年2月、大学4年の最終学期に私は、なるべく容易に卒業単位を取得するためだけに日本史の授業を選択した。
しかしこの授業は、そんじょそこらの日本史の授業ではなかった。
まず教えていたのが、今では世界的に知る人ぞ知る哲学者となったウィリアム(ビル)・へーバーだった。
彼がシカゴ大学の博士課程に在籍していた当時、東大と京大で西田幾多郎を研究していたこともあったへーバーは、日本の事情にも通じていた。
僕は受講していなかったある別な授業でへーバーは、教室に入ってくるなり黒板に漢字で「『構造と力』、浅田彰」と大きく書き、まだ米国でほとんど全く知られていなかったデリダやドゥルーズ&ガタリについて書かれた浅田さんの本がいかに優れているか、そしてそれを若干26歳で書いた浅田さんが、世界的にみても稀にみる天才であるかを延々と語りだしたことを、その授業を受講していた友人から聞いていた。
そんなへーバーゆえ、論文のトピックも独特極まりないものだった。
「山本常朝の『葉隠』(1716)、平賀源内の『放屁論』(1774)、勝小吉の『夢酔独言』(1843)を通して、江戸期における主体性の変遷を論じよ」
これが最初の論文のトピックだった。
周囲の生徒はパニックに陥っていたが、僕は咄嗟にアイディアが沸き、ノリノリで一晩で書き上げた。
そのアイディアとは、『葉隠』を柄谷さんの『探求I』とウィトゲンシュタインの『哲学探究』と、『放屁論』と『夢酔独言』をそれぞれ、浅田さんの『構造と力』、『逃走論』、ニーチェの『喜ばしき知恵』、そしてドゥルーズ&ガタリの『アンチ・エディプス』とミックスして論じるというものだった。
へーバーはこの論文(特に浅田さんとドゥルーズ&ガタリを用いての『夢酔独言』読解)をいたく気に入ってくれて、それで博士号取得、大学教授への道が開けたというわけだ。
それから25年後の2016年、『A Secret History』を書いている時に、『夢酔独言』こそ、バガボンディズム(=「A/D」)としての「いき」の究極の表現の一つであることを悟った。
そして大学を去り、本格的に「Xへの道」を歩み出した。
7.『べらぼう』
『夢酔独言』にまつわるこんな大昔の話まで思い出したのも、『新ジャポニズム』を観て「NHKオンデマンド(以後、「オンデマンド」)ぐらいは加入しておこう」と思ったことに端を発する。
さらに言えば、『Xへの道、あるいはシン高物語(28)』で書いた通り、出来るだけ母と多くの時間を過ごそうと思い、一緒に居間で『新ジャポニズム』を観たことに。
「オンデマンド」では蔦屋重三郎にまつわるNHK大河ドラマ『べらぼう』の第一回目が配信されていた。
史実的にも「いき」誕生の立役者の物語だ。
なんというめぐり合わせだろう。
勿論、NHK大河ドラマは、「B」もしくは「C」(主に前者)の支配的地位の維持を意図していると考えるのが妥当だろう。
それを「メンバー(=バガボンド)」は「A/D」へとリミックスし、「バガボンディズム(=「いき」)の拡充」としての「Xの文化」を構築していくのだ。
シン高が開校する年の大河ドラマが「「いき」の誕生物語」であることに、運命的なものを感じずにはいられない。
そもそも「Xへの道」は元々、NHK大河ドラマとの強い繋がりを持つ。
ともに三谷幸喜脚本による『新選組!』(2004,観たのは2008)と『真田丸』(2016,観たのは2018)が、「Xへの道」を進むよう僕の背中を押した(この件についてはまたいずれ書く)。
果たして『べらぼう』はどうか。
そこからどんな「「いき」=バガボンディズム」が構築されるのか。
楽しみでしょうがない。
8.『攻殻機動隊』
指導教官としての最後の大学院生の一人に、中国の最高学府である北京大学を卒業した学生がいた。
少なくとも彼が学部生として北京大にいた2000年代後半からすでに、大学のコンピューター・ルームはNHK大河ドラマを観ようとする学生に占拠されていたという。
このことから、マンガ・アニメだけではなく日本のドラマも、中国をはじめ世界中に多くのオーディエンスを持つと考えられる。
ましてやネトフリ隆盛の現在なら特に。
そうして考えると、マンガ、アニメ、ドラマを通して「バガボンディズム(=「A/D」としての「いき」)」を拡充することが、最も効果的と思われる。
言うまでもなく、この目的に適した作品でなければならないが、バガボンディズム自体が、常に進化(=「リミックス」としての脱構築)し続けるものだから、そうした作品自体も増殖し続けることになる。
勿論それらは、エンタメ作品だけに限らない。
基準はたった一つ、バガボンディズムの拡充に必要ということだけだ。
この基準さえクリアされれば、小説、映画からアートまで、あらゆる作品が対象となる。
「バガボンド」(=「(シン高および幸和グループ)メンバー」)は、剣をAIに変え、「Xへの道」をゆく。
それゆえ、『新ジャポニズム』を観て即座に思い浮かんだのが、『攻殻機動隊』だった。
およそ20年前からこの作品に描かれていることが、シンギュラリティ前夜の今、次々に現実になっている。
以前どこかで、子どもの頃に『攻殻機動隊』を観て、大人になったら実際に同じものを作りたいと思い研究者になり、実際に作ってしまっている人が少なからずいるという記事を読んだことがある。
その記事は日本に限っての話だったが、そうした人は世界中に大勢いるだろう。
色々調べていくうちに、シンギュラリティを梃に「X」の実現を目論む僕を魅了する『攻殻機動隊』の側面が、原作漫画に、否、正確に言えば原作者である士郎正宗のうちに存することが、彼のインタビューを読んで明らかになった。
これによると、彼は中学一年生の時から『日経サイエンス』を愛読しており、以来、現在に至るまでそこで得た知識が作品に反映されているらしい。
僕も中一ごろから「講談社ブルーバックス」を読んでいたが、『日経サイエンス』となるとチンプンカンプンだった(せいぜい『Newton』どまりだった)。
だから士郎がどれほどずば抜けた頭脳の持ち主かがよく分かる。
それゆえ今後は、士郎の作品を「AIの世界への窓」としながら、シンギュラリティ学者兼AIジャーナリストを目指してゆく。
9.『ダンダダン』
ほとんど『攻殻機動隊』を全シリーズ観るためだけにネトフリに再加入した。
そこで「新ジャポニズム」を通して世界的に人気を博していることを知った『ダンダダン』を観た。
これほど笑わせてくれる作品に出会ったのは、映画『下妻物語』以来だ。
どちらも女子高生が主人公だ。
女子高生が主人公と言えば、my all-time best filmsの一つである山下敦弘監督による映画『リンダリンダリンダ』もそうだ。
この映画のラスト30分(はぴいえんどの「風来坊」が流れる辺りから)は、何十回観ても毎回、嗚咽するほどの大号泣ものだ。
僕を大笑い・大泣きさせる作品には、女子高生を主人公としたものが多い(ちなみに僕の高校は男子校だった)。
よくよく考えてみれば、もう一つのmy all-time best filmである押井守監督(映画『甲殻機動隊(Ghost in the Shell)』の監督)による『うる星やつら2 ビューティフルドリーマー』の主人公も女子高生であった(人間ではなかったが)。
『Xへの道、あるいはシン高物語』も高校生(シン高生)が主人公であり、勿論そこには女子高生をはじめ、あらゆるジェンダー and/or セクシュアリティの人々が含まれる。
「バガボンド」に性差はない。
というわけで『ダンダダン』だ。
様々な意味で素晴らしい。
一言で言えば全てが「いき」だ。
会話(言葉遣い)も、グラフィック・イメージも、演出も、編集も、音楽も、何もかも。
疲れ果て、『攻殻機動隊』をはじめ多くの作品が小難しく感じられる夜寝る前、今唯一観たくなる作品は『ダンダダンダ』だ。
僕は小さい頃からとても怖がりで、怪談は大の苦手なはずだが、この作品だけは例外だ。
ややこしいこと抜きに、明日への活力を与えてくれる作品。
それもバガボンディズム(=「X」の文化)を表現する作品の大切な要素だ。
(続く)