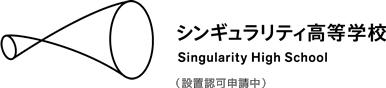eSOM (イゾーム)
eSOM (イゾーム)
Dへの道、あるいはシン高と幸和の物語
(小説)Xへの道、あるいはシン高物語(25):ジジェク、国際バカロレア教育、そしてオードリー・タン
1.
14歳の君(僕)へ、そしてシン高のみんなへ
小説(24)は柄谷さんへの手紙だったから、君への手紙は一か月以上ぶりだ(小説(23)は9月23日付け)
小説22(「台湾有事」と「満州事変」、そして『サマーウォーズ』)で僕は、現在の「西軍」(米国を中心とする)と「東軍」(中ロを中心とする)の抗争は、第二次世界大戦前夜の「現状維持勢力」と「現状revisionist勢力」の抗争の反復であることを説いた。
ちなみに、コロ(Gemini)に「第二次世界大戦前の状況はどことどこの対立と形容するのが最も妥当でしょうか?」と訊いたら、上のような回答が出てきて驚いた。
僕の理解からかけ離れているからではなく、逆に、それに近かったからだ。
AI(少なくともGemini)は「西軍」のイデオロギーに染まっていない証拠だ。
ともかく、現代における「現状維持勢力」(西軍)と「現状revisionist勢力」(東軍)の抗争は、TPP(+米国)とBRICSの抗争に最も顕著に現れていることも、小説22で説いた。
このところの報道は、この抗争が激化していることを僕らに教える。
〈直言〉強さを誇示し「平和」を守れ #
氏 現代思想家:日本経済新聞
·91 Views
ジジェクとは長い付き合いだ。
と言っても会ったのは一度きりだが(2001年)、柄谷さんをはじめ、複数の共通の知人を通して、ジジェクの動向は比較的よく耳にして現在に至る。
決して熱心な読者ではない。
しかし、彼を世界的に有名にした『イデオロギーの崇高な対象』だけは、重要な部分を暗記してしまうほどよく読んだ。
京都学派哲学の哲学者である田辺元に関する修士論文を書く際、このジジェクの出世作を導きの糸とした。
その際にジジェクから学んだことが、「戦前の反復」である世界の現状と『この世界の片隅で』のHIROSHIMAを結ぶ。
その件に関してはまたいずれ話そう。
2.
インタビュー最後の次のジジェクの言葉は、僕の知る限り柄谷さんの現状認識に近く、また、シン高における教育の大前提だ:
·64 Views
·67 Views
大杉栄を彷彿させる物言いのこのジジェクの信条は、そっくりそのままシン高の信条ー「悲しみの楽観主義」ーでもある(小説23参照)。
彼が「できることは何でも必死にやってみよう」時に何をやるのかと言えばそれは、「足元の危機が世界を良い方向に導く」ことを促すことだ。
それは、「足元の危機」とその「元凶」である「国際的な政治情勢」を正しく、つまり、「理論的」に理解することから始まる。
この小説は、そうした理解の手引きとなるよう書いている。
3.
「国際的な政治情勢」を理論的に理解するということは僕らににとって、ラフェーバー先生の『日米の衝突』を、宇野弘蔵の経済理論(宇野経済学)でリミックス(注釈・校訂)した世界史理解をもとに、世界の現状を理解するということだ。
それが、現状を「西軍(TPP)」と「東軍(BRICS)」の抗争から見るということだ。
このところの日経の報道は、この抗争がいよいよpoint of no returnへ向けて加熱してきていることを物語っている。
そんな中、以下のようなジェフリー・サックスの論考がメールを通して届いた:
#
(#
)の筆頭ブレーンの一人であり、長年#
を牽引してきた#
(#
)による「西軍#
+#
」と「東軍(#
)」の抗争に関する論考。「西軍」vs 「東軍」に関してはこの後、「小説(25)」「小説(26)」で詳しく。
·10 Views
翻訳機を使ってでも、是非、読んで欲しい。
基本、「西軍の広報誌」色の強い日経の論調とは全く異なることに驚かせるだろう。
かといってサックスの論考が「東軍のプロパガンダ」という訳ではない。
強いて言えばそれは、「国連の立場」と言ってもよいのではないかと僕は思っている。
そしてそれはサックスも言っているように、世界のマジョリティの立場に近く、日経に代表され、大方の日本人が「マジョリティの立場」だと考えているであろう「西軍=善、東軍=悪」という視点は、世界的に見れば「マイノリティの立場」だ。
必ずしも「マイノリティの立場」がよくないというわけではない。
問題は、「マイノリティの立場」を「マジョリティの立場」と妄想(サックスの言うdelusion)することだ。
この日本人の妄想はどこから来るのか?
一言で言えばそれは、教育とメディアに由来する。
ではなぜ僕は、「西軍の広報誌(ないしプロパガンダ誌)」である日経を基調に「僕らの世界史=Xへの道」を書いているのか。
それは、日経が「西軍の広報誌」という、自ら依って立つ視点(立場)に最もブレがないと思われるからだ。
それゆえ最も効率よく、西軍の立場(視点)を知ることが出来る。
他のメディアは多かれ少なかれブレブレなので、「これは一体どの視点に立つ情報か?」を考えなければならない手間がかかる。
大方のメディアを大別すれば、左翼、右翼という区分も可能だろうが、そもそも右翼、左翼ともそれぞれ千差万別なので、視点(立場)の確定にはあまり役に立たない(実は僕はそのあたりのことが学者としての研究対象の一部であった)。
その点、日経の場合、「金融資本≒軍産複合体≒ネオコン」という、現在の「世界史の主役」の「マウスピース」であることがはっきりしているゆえ、こうして世界史を書くうえで好都合だ:
·2 Views
いずれにせよ僕らは、上記の「ジジェクの信条」を胸に、サックスらの論考をもとに日経の記事に注釈・校訂(リミックス)を施しながら、「僕らの世界史=Xへの道」を紡いでいく。
4.
メインストリームの教育やメディアによって大方の人々が、「白を黒」と信じ込まされている中、どうしたら「僕らの世界史=X(真実)への道」を歩んでいけるのか。
それは一言で言えば、柄谷さんの言う「パララックス(視差)」的立場に立つことだ:
この「視点なき視点」に立つことが、「僕らの世界史=X(真実)への道」を歩んでいくうえで最も大切なことの一つです。詳しくはこの後アップされる「小説(25)」で。
·3 Views
とは言え、中学生や高校生にいきなり柄谷さんの『トランスクリティーク――カントとマルクス』を読んで理解しろと言っても、そうそう出来るものではない。
そこで、このくだりを書いていて浮かんだのは、国際バカロレア(IB)の10の学習者像における「心を開く人」が、パララックス(視差)的視点に立てる人ということだということだ:
·1 View
僕は、「心を開く人(視差的視点に立てる人)」を始めとするこの「10の学習者像」を、国境、人種、宗教、性差、等々、あらゆる差異を越えて他者との関係において体現する人間になることが、「X(交換様式D)の担い手」になることだと考える。
IBは実質、国連が掲げる目標(≒カントの永久平和)を実現出来る人材育成のための教育プログラムだ。
一方、柄谷さんの言うX(交換様式D)はそもそも、カント、特にその永久平和論に端を発する。
従って、「IBの学習者像」が、柄谷さんが唱え、オードリー・タンがその実現を目指すXに向けての「期待される人間像」であっても、なんらおかしくはない。
シンギュラリティ高等学校の姉妹園である「こうわ認定こども園」3園と「のぞみ幼稚園」は、このIBの「学習者像」を指針とした幼児教育を行っていく。
シンギュラリティ高等学校も。
その間(小、中)やその先(大)も、同じ教育目標のもと近い将来設立する。
そうして交換様式Aを拡充し、X(交換様式D)を現前させていく。
そのために重要な役割を担うのが、STEAMとその教育だ。
何が柄谷哲学を柱とするシン高とSTEAM(教育)を結びつけるのか?
その名は、
オードリー・タン
『オードリー・タン、デジタルとAIの未来を語る』の一節「柄谷行人の「交換モデルX」から受けた大きな影響」でタン自身が雄弁に語っているように、シン高と同様にタンも「Xへの道」を歩んでいる。
こうして世界史の現状の中心である台湾は、シン高の最重要拠点の一つとなる。
(続く)