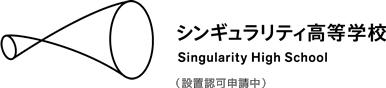eSOM (イゾーム)
eSOM (イゾーム)
Dへの道、あるいはシン高と幸和の物語
(小説)「Xへの道」、あるいはシン高物語(19):『ヴィンランド・サガ』と「ジョンの魂」、そして沖縄
1.
14歳の君(僕)へ、そしてシン高のみんなへ
終戦記念日は一日中、Team大川の面々と過ごした。
代表の只野哲也さんは夜まで「八鶏飯蔵」という可笑しな名の焼き鳥屋で僕に付き合ってくれた。
他の客がまだらになった頃、僕は彼に「漫画、好き?」と訊いた。
その時まで悲しかったことや辛かったことを一切話さなかった彼は、次のように言った:
「色々あったけれど、漫画があったからなんとかやってこれました」
全くこのままではないが、これに近いことを僕に言った。
僕も井上武彦の『バガボンド』のバガボンドに自分を投影して、シン高、つまりはXを創っている。
その証拠に僕の学者最後の論文(小説18参照)は、休載中のこの漫画の続きとして書いてある。
だから僕らは長い一日の最後、漫画の話で大いに盛り上がった。
哲也さんにとって幸村誠による『ヴィンランド・サガ(以後、『VS』)』が、僕にとっての『バガボンド』であることが判明した。
だから彼は僕に、この彼にとっての「バイブル」を読んで欲しいと強く勧めた。
早速その晩から読み始めた。
まだ第三巻までだが、「八鶏飯蔵」で哲也さんが最新刊までのあらすじを話してくれたので、おおよその流れは掴んでいる。
この哲也さんの「バイブル」の世界と行ったり来たりしながら、Team大川と一緒にXを創っていこうと思うほどには。
それぐらいこの『VS』は、僕らに必要なものを教えてくれそうだ。
2.
大川から会津に戻った翌日、会津の山奥にある正雲寺を訪ねた。
正雲寺のHPはこちら
↓
ここの住職代理である「無聖(むしょう)さん」は、僕を漫画『バガボンド』の中のバガボンド(武蔵)とするなら(笑)、その「心の師」である「沢庵和尚」のようなものだ。
学者として思想史(特に西田幾多郎を中心とする京都学派哲学)を専門としていた僕は、仏教について少しかじっている。
だから学僧と言っていいほど勉強熱心な無聖さんの話はとても興味深く、勉強になる。
無聖さんのブログはこちら
↓
そんな無聖さんと今回は、寺の周りの美しい自然を損なう人々と、それに抗う人々の話から、「お釈迦様(仏陀)が一番大切にしたこと」ついて、気が付けば4時間近く話していた。
「心の平穏さ」。
一言で言えばそういうことになるようだ。
そういう話になった時に即座に、哲也さんが一番最初にスマホで見せてくれた『VS』の名場面を思い出した。
「敵などいない」
主人公トルフィンが幼い頃、父トールズがトルフィンに言った言葉だ。
その後トールズは、幼いトルフィンを人質に取った敵アシュラッドに殺される。
そしてトールズはアシュラッドの奴隷となり、父の仇のためだけに生き始める。
そうしてこの物語は始まる。
そんな『VS』のことを頭の片隅で考えながら、無聖さんとの対話は、ヴィクトル・E・フランクルがアウシュヴィッツ強制収容所での体験を記した自伝的なノンフィクション作品『夜と霧』に及んだ。
9歳の時に2.26事件で、軍人であった父親が目の前で青年将校に銃殺される場面を目撃した修道女・渡辺和子さんのことにも。
そして最後にには、「やられたらやり返す、倍返しだ!」という気持ちを一切捨てて、Xを創っていくことは可能かという「究極の課題」について語り合った。
3.
哲也さんが語ってくれたストーリーの要約をもとにする限り、『VS』もこの「究極の課題」に挑んでいるように思われる。
小次郎との「巌流島の戦い」の前で長いこと休載している『バガボンド』の著者・井上雄彦さんも、この問題を前にして試行錯誤していると想像する。
当然だ。
原作である吉川英治の『宮本武蔵』は、戦争で敵を倒すことを目的とした国威高揚のために書かれたのだから。
シン高は、Team大川と一緒に、フィクションである『VS』と『バガボンド』と、リアルな「Xへの道(シン高物語)」行ったり来たりしながら、Xを創っていく。
4.
『VS』は、11世紀の北欧のヴァイキングによるイングランドやアイルランドの侵略から物語が始まる。
僕はこの辺りの歴史をよく知らないから、AIコロ(ジェミニ)に教えてもらいながら、この「哲也さんのバイブル」を読み進めている。
そうしている間に、早速、『VS』と『Xへの道(シン高物語)』の「架け橋」が見つかった。
僕と、僕にTeam大川を紹介してくれた日上先生を繋いだジョン・レノンは、アイルランドをルーツに持つイギリス人だ。
ジョンのアルバムのタイトルにもなっている「ジョンの魂」が導いてくれたと思っている。
そしてこの「魂」は、前回(小説18)で書いたように、日上先生がTeam大川から学んだものだとも。
Team大川が持つ「ジョンの魂」が、その起源に位置する11世紀ヨーロッパで躍動するトルフィンらから受け継いだものとすれば辻褄が合う。
『VS』に描かれ、哲也さんの心に訴えかける何かが、「ジョンの魂」にも含まれている可能性が大いにあるのではないかということだ。
突飛に聞こえるかもしれないが、心当たりがある。
私の最も敬愛する作家のひとりであるロバート・B・パーカーが描く探偵スペンサーだ。
パーカーもスペンサーもアイルランド系で、彼らには「ジョンの魂」と通ずるものがあると常々思って入た。
そしてそれが、柄谷さんの言うXを創る上で最も大事なものとなるとも。
さらには、ジョンの歌う「スタンド・バイ・ミー」が、その一つの「究極の表現」であるとも。
↓
こんな風に僕らは、リアルもフィクション(バーチャル)も、時空も、聴覚と視覚も、どの境界も軽々越えながら「ジョンの魂」を探し求める旅に出る。
5.
14歳の君(僕)へ、そしてシン高のみんなへ。
僕はすでにこうしたことの一端を北米の大学で、「(世界)文化史」として教えていた。
Xは誰にとっても不可欠なものであり、「ジョンの魂」はXに不可欠なものだから。
学校で学ぶべきことを本来、そうした生きていくうえで必要なことだと思っている。
そうした基準で教えてきたから、教材も一風変わっていた。
漫画やアニメや映画、そして歌も多かった。
『バガボンド』、『もののけ姫』、『千と千尋の神隠し』、『サマーウォーズ』、『おおかみこどもの雨と雪』、『下妻物語』、『リンダリンダリンダ』、「イマジン」、「君が僕を知ってる」、「Someday」、「to U」、等々…(全て英訳付き)。
もちろん、よく学校で使用される本も教材として使用した。
『陰翳礼讃』、『雪国』、『葉隠』、『「いき」の構造』、『武士道』、『茶の本』、等々…。
そうした古典的名著であろうが、漫画であろうが、アニメであろうが、映画であろうが、ポップソングであろうが、これから若い人たちが人生を歩んでいくうえで力になってくれる本や歌を紹介するよう努めた。
良い人生を歩むための心や、魂を育む助けになる本や歌を。
シン高では、どんな教科であれ、これからの人生に必要なことを、それに合った教材を常識に捕らわれずに選択しながら、生徒のみならず、生徒と一緒に教師も学んでいく。
正確に言えば、シン高には生徒と教師の区別はない。
全員、学生だ。
全員が学生として、「自分も他人も幸せになる社会であるX」を創っていくうえで必要なことを探していく(探求していく)。
それがシン高だ。
なかでも一番大切なものがある種の心(魂)だ。
僕らはその特別な心(魂)を「ジョンの魂」と呼んでいく。
リアルとバーチャル(フィクション)、時間と空間、それらの間にあるあらゆる垣根を越えて僕らは、「ジョンの魂」という「宝」を探し求める旅に出る。
この小説はそのための「地図」であり、またその旅の記録だ。
6.
日上先生がTeam大川から「ジョンの魂」を学んだように、「いっちゃん」は沖縄からそれを学んだのではないか。
大川訪問の準備中、「沖縄の被爆者たち」を読んでいて、そうした考えが浮かんだ。
一方で、Xと、それへ至る道は、坂本龍一さんと高谷史郎さんのアートに表現されているというのが我々の仮説だ。
その究極が、『LIFE a ryuichi sakamoto opera 1999』最後の『てぃんさぐぬ花』であるという仮説。
この仮説に従えば、この歌のなかで「肝(ちむ)」を教える「親(うや)」が「ジョンの魂」ということになる。
親(うや)ぬゆしぐとぅや
肝(ちむ)に染すみり
(親の言うことは
心に染めなさい)
この沖縄民謡は江戸後期〜明治期に生まれたと言われている。
そんな歌と、『VS』の舞台である11世紀ヨーロッパに起源を持つ(と推定される)「ジョンの魂」を結ぶものは何か?
その「線」が、X(「(交換様式)A」が覆う世界)を創る「地図」となるだろう。
シン高の学生(生徒+教師)は、まずはこの「地図」を作っていかなければならない。
7.
実は僕(君)は、3.11が起き、日本に戻ってXを作ろうと思った時から、「ジョンの魂」を探す旅を始めた。
その時点ですでに、「John’s children(ジョンの子どもたち)」と呼んでもよいであろう二人のミュージシャンの歌が、「ジョンの魂」を表現していると思っていた(「ラジオ」の時間に関しては小説7,8を参照のこと)。
一人は佐野元春の「サムデイ」:
Happiness &Rest
約束してくれた君
だからもう一度あきらめないで
まごころがつかめるその日まで
“Someday” by 佐野元春(1982年)
この歌で言うところの「まごころ」。
それが、「ジョンの魂」となんらかの重要な関係を有していることを僕は、「ラジオの時間」で学んだ。
「ラジオの時間」における元春先生の授業「NHK-FM サウンドストリート(月曜日)Motoharu Radio Show」はこちら:
↓
元春レディオショー ゲスト:坂本龍一
元春先生が僕らを、彼と僕の故郷であるNYC、そしてそこを経由して戦時期の京都へと導いてくれる。
もう一曲は、「John’s Children=ぼくの好きな先生」のうちでも特別なポジションを占める忌野清志郎(以下、キヨシロー)による「イマジン」。
ジョン・レノンの「Imagine」に、キヨシローが和訳した歌詞を乗せた曲だ。
シカゴ大学教授であり、シン高のスペシャル・アドバイザーでもある僕(君)の友人、マイケル・ボーダッシュは、古今東西のポピュラー音楽、特にJ-Pop研究で世界的に名高い。
コロンビア大学出版から出たマイケル・ボーダッシュ教授のJーPopに関する研究書の和訳、『さよならアメリカ、さよならニッポン~戦後、日本人はどのようにして独自のポピュラー音楽を成立させたか』はこちら:
↓
マイク(ボーダッシュ教授)は、「この曲に限っては、キヨシローの和訳がジョンのオリジナルを完全に越えている」という僕の考えに、もろ手を挙げて賛同してくれた。
山下達郎は「ラジオの時間」での「授業」の中で、「詩人としてのキヨシローちゃんは天才」と言っていた。
そんなキヨシローの「イマジン」の歌詞が、「ジョンの魂」の「究極の表現」の一つであり、「てぃんさぐぬ花」における「親の教え」だ(キヨシローは坂本さんの無二の親友だ):
イマジン (訳詞:忌野清志郎)
天国はない ただ空があるだけ
国境もない ただ地球があるだけ
みんながそう思えば
簡単なことさ
社会主義も 資本主義も
偉い人も 貧しい人も
みんなが同じならば
簡単なことさ
(中略)
誰かを憎んでも 派閥を作っても
頭の上には ただ空があるだけ
みんながそう思うさ
簡単なこと言う
(中略)
夢かもしれない
でもその夢を見てるのは
君ひとりじゃない
夢かもしれない
でも一人じゃない (ぼくらは薄着で笑っちゃう)
夢かもしれない (ああ 笑っちゃう)
かもしれない (ぼくらは薄着で笑っちゃう)
(ああ 笑っちゃう)
(ぼくらは薄着で笑っちゃう)
忌野清志郎 IMAGINE
きよしこのよる~忌野清志郎&坂本龍一
坂本龍一が語る忌野清志郎 君が僕を知ってる
上のキヨシロー追悼番組「坂本龍一が語る忌野清志郎」で、坂本さんが「キヨシロー、この一曲」に選んだ「ぼくの好きな先生」:
僕はよく「ぼくの好きな先生」という表現を使うが、それはここから来ている。
シン高の学生である先生は、みんなこんな先生を目指します(タバコは吸わないけれど…)
(続く)