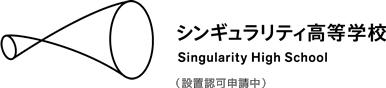eSOM (イゾーム)
eSOM (イゾーム)
Dへの道、あるいはシン高と幸和の物語
eSOM: Dへの道(33)ストレス、フローの最大の敵、Part 1
1.
前回(第2回目)のスクーリングが終わったと思ったら、また次(第3回目)のスクーリングがやってきました。
この間に、シン高にとって大きな出来事が起こりました。
オードリー・タン氏と一緒に、彼女が唱えるデジタル民主主義社会を、東地中海経済・文化圏(EMECS)として構築していくことが決まったのです。
『eSOM: Dへの道』(21~30)である「オードリー・タンの『Good Enough Ancestor』を観ながらシン高を構築する」を彼女に読んでいただいたところ、彼女がその内容に賛同してくださったのです。
EMECSの構築自体は、シン高の姉妹組織である㈱eSOM(イゾーム)が担います。
シン高と、数年以内に設立する「大学」は、その構築を担う人材を育成することが役目です。
(大学が「」付きなのは、それが現存する大方の大学とは大きく異なる、今後300年間の高等教育のモデルものとして構築することを目指すからです。)
EMECS構築のための共育は、脳の構造の理解が根本基礎となります。
なぜなら、E. グレン・ワイルとタン氏の共著『Plurality』によれば、脳の構造自体が、EMECSの構造そのものと言っても過言ではないからです。
そして、脳の構造(=EMECSの構造)の学びの端緒となるのが「体育」であり、そのテキストが『運動脳』です。
3
今回(第3回)の体育のスクーリングでは、『運動脳』第2章をもとに、フローの天敵であるストレスを軽減するのに、ランニング/ウォーキングがどのように脳に作用するのかを探求します。
その前にまず、前回の内容の復習から始めましょう。
シン高においては、家庭科と保健体育が、他のあらゆる学びの前提となります。
それがなぜかをQ&A形式で振り返りましょう。
Q1. なぜシン高においては、家庭科から全ての学びが始まるのでしょうか?
A1. シン高の共育方針は、様々な学びを開始する前にまず、自分の人生の目標と、そこに到達するための道筋を明らかにし、その目標に到達するために、他の全ての学びを行います。
シン高では家庭科において、その目標を出来る限り明らかにし、そこに到達するための道筋を明らかにします。
Q2. そうした家庭科の役割と密接に関連した保健体育の役割とはいかなるものでしょうか?
A2. シン高において、自分の人生の目標とは、自らのフロー(時間を忘れて没頭出来ること=好きなこと)と、人類が目指すべき社会(SDGsが達成された社会≒ウェルビーイング社会≒D=DD)の構築に必要とされることの接点のことです。
となると、まず、フローとは何かを理解し、出来るだけ長く、そして深く、フローに入れなければなりません。
シン高の保健体育は、「出来るだけ長く、そして深く、フローに入れる脳(=フローな脳)」をランニング/ウォーキングを通して構築しながら、(フローな)脳と身体のメカニズムを科学的に理解する役目を担っています。
Q3. フローな脳を構築するという目的以外にもう一つ、シン高においては、脳のメカニズムを学ぶ重要な目的がありますよね?
A3. シン高において脳の構造/メカニズムを学ぶにあたっての、二つ目の目的とは、複雑な脳の構造/メカニズムは、同様に複雑な社会の構造/メカニズムと基本同じであるという前提に立ち、他教科で社会の構造/メカニズムを学ぶうえでの根本基礎を習得するということです。
2.
Q4. 前回のスクーリングで学んだ、ランニング/ウォーキングによって脳が活性化され、フローに入る(=集中力/選択的理解力が高まる)メカニズムとは、どのようなものでしたか?
A4.
-
まず大事なのは、フローは「集中力/選択的理解力の高まり」であり、この「集中力/選択的理解力」が、「意識(=様々な知覚(視覚や聴覚など)をすべてふるいにかけ、今、脳が集中すべきものと重要でないものを判別する脳の働き)」と呼ばれるものであるということです。
-
そしてこうした意味での「意識」は、前頭葉と側頭葉に頭頂葉を加えた大脳の三つの部分(葉、よう)の連携(コラボレーション)の産物です。
-
特に前頭葉の前の部分の前頭前皮質は、「その場の思いつきで行動せず長期的目標を設定し達成するの力」、つまりは、コンピュテーショナル・シンキング(CT)の源泉であるゆえ、「脳の司令塔」と見做されます。
-
前頭葉、側頭葉、頭頂葉といった主体(≒エージェント)の連携(コラボ)が上手くいけばいくほど意識が高まる(集中力/選択的理解力)が高まる)ことになるわけです。
-
これはサッカーで言えば、選手(=エージェント)間の連携(コラボ)が上手くいけばいくほど勝利に近づくことや、あるいは、社会成員(=エージェント)間の連携(コラボ)が上手くいけばいくほど、個人と社会両方のウェルビーイングが高まり、社会はDD=Dに近づくことと同じです。
-
「報酬系」というシステムの役割
-
脳のエージェント間のコラボをより円滑にし、フロー(意識/集中力/選択的理解力の高まり)を生じせしめるのが「報酬系システム」です。
-
報酬系は、側坐核(報酬中枢)という脳の部位を中心としたシステムです。
-
ある行動(例:性行為)が、なんらかの理由で自分の欲求を満たす場合、側坐核におけるドーパミンの分泌量が増加する形で、「性行為は欲求を充足する(=報酬をもたらす)行為である」という情報が生成されます。
-
ドーパミンをもとに側坐核で生成されるその情報が、これまたドーパミンによって前頭葉(特に前頭前皮質)に伝達され、そこで「性行為を行いたい」という欲求(としての意識)が構築される。
-
前頭葉が「性交したい」という欲求=意識を構築する際も、その材料となるのはドーパミンである。
-
フロー(時間を忘れてあることを継続しようとすること)の源は、こうした欲求=報酬であり、欲求=報酬の源泉(=材料)はドーパミンである。
-
従って、ドーパミンがフローを構築するための「材料(源泉)」ということになる。
-
ランニング/ウォーキングは、フローの「材料」であるドーパミン(快楽物質)の脳における分泌量を増加させる。
Q5 社会において、脳のネットワークに相当するものは何だと思いますか?(この質問は是非、投げかけていただければと思います。)
3.
では、『運動脳』第三章「脳から「ストレス」を取り払う」をもとに、ランニングやウォーキングがどのように脳に働きかけ、脳から「ストレス」を取り払うのかを学んでいきましょう。
まずはコロぴょんによるストレスの定義は以下の通り(黒太字):
ストレスとは、外部からの刺激や変化に対して、心や体が適応しようとする際に生じる反応のことです。
これらの刺激は、物理的なもの(騒音、暑さ、寒さなど)や心理的なもの(人間関係、仕事のプレッシャー、将来への不安など)まで多岐にわたります。ストレスを感じると、心拍数が上がったり、筋肉が緊張したり、集中力が散漫になったりするなど、さまざまな身体的・精神的な反応が現れます。
Q6 あなたはどのような時にストレスを感じますか?
コロぴょんが言うように、「ストレスを感じると、集中力[フロー]が散漫にな」ります。
では、ストレスが生じる時、脳では何が起きているのでしょうか?
-
偏桃体(へんとうたい、脳の部位の一種)が危険を察知し、視床下部(H)、下垂体(P)、副腎(A)からなる「HPA軸=副腎軸」という体のストレス反応やホルモンのバランスを調節するシステム(経路)に「警告」を発する。(66頁)
-
警告(=脅威)を受け取ったH(hypothalamus、視床下部)がホルモン(CRH、副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン)を放出してP(pituitary、下垂体)を刺激する。(以下、7まで63~8頁)
-
Q. コロぴょん、ホルモンについて様々な角度から詳しく教えてください。
-
P(下垂体)は別なホルモンを放出し、そのホルモンが血流によって運ばれ、A(adrenal gland、副腎)を刺激する。
-
それを受けて副腎は「コルチゾール」(ストレスホルモン)を放出する。
-
結果、コルチゾールの血中濃度が上がり、脳も身体も厳戒態勢(ストレス反応)に入る。
-
ストレス反応(脳と身体の「厳戒態勢」)=「自分の命を守るため、闘争あるいは逃走の準備が整うと、筋肉がたくさんの血液を必要とするために、動悸が激しくなる(=心拍数が増加する)」。
-
ストレス反応は偏桃体(HPA軸の動力源)をさらに活性化し、上記のプロセスを通してストレス反応を増幅する。
-
偏桃体の興奮が治まらず、HPA軸が制御不能の状態になれば、そのうちに本格的なパニック発作が起こる。
-
パニック発作は非常に辛いだけでなく、発作を起こした人が理性を失った行動に出がちで、いい結果に終わることは少ない。
こうした脳の活動によって起こるストレス(反応)は、フローを基にウェルビーイングを高めるどころか、自分も他者も不幸にする元凶となります。
そこでランニング/ウォーキングは、ストレスを低減し、フローを活性化し、結果、ウェルビーイングを高めることに大いに役立ちます。
『運動脳』は、脳には「ストレス反応を緩和して、興奮やパニック発作を防ぐブレーキペダルがいくつか備わっている」と言います。(68頁)
運動は、それら「ブレーキ」の効きを良くするということになるわけですが、まずはその二つの「ブレーキ」を見てゆきましょう。
(続く)