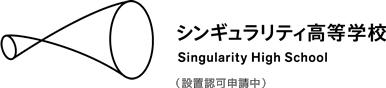eSOM (イゾーム)
eSOM (イゾーム)
Dへの道、あるいはシン高と幸和の物語
eSOM: Dへの道(16)新HP/パンフ草案2~脳と運動、あるいは論述力とコンピュテーショナル・シンキング~
1.探求学習
自分が「構築すべきもの/構築したいもの」をまず作り出し、それを作りながら「学ぶべきこと/学びたいこと」を学ぶ。
これがシン高の共育理念である構築主義です。
構築主義を実践するには、フロー(時間を忘れて何かに没頭する状態)に入る必要があります。
時間を忘れて没頭する状態?
何も難しく考える必要はありません。
フローとは、子どもがプラモデル作りやお人形遊びに熱中し大人の声が届かない時の、あの状態のことです。
では、どうすればフローに入れるのでしょうか?
このように、ある一つの理解(例:「構築主義を実践するにはフローに入る必要がある」)から、それを深堀する問い(課題)を次々に導き出し、それを解決していくことを探求学習と言います。
シン高生の最大の目標は、探究学習者になることです。
つまりバガボンドになることです。(『eSOM』(15)参照)
構築主義、フロー、探究学習者、バガボンド。
これらのことをまず家庭科で学びます。
2.フローとゾーン
では、どうすればフローに入れるのでしょうか?
シン高の保健体育は、この課題を探究していきます。
保健体育の担当ファシリテーターは畑祐喜(はた ひろき)さんです。
優秀なサッカー選手でもあった畑さんは、シン高サッカー部の監督でもいらっしゃいます。
畑さんは、サッカー選手として沢山のフロー体験をお持ちです。
フローは、スポーツでよく言われるゾーンと、とてもよく似ていると言われています。
Q. ミハイ・チクセントミハイの概念「フロー」は、スポーツでよく言われる「ゾーン」とてもよく似ていると言われます。フローが基本的にゾーンと同じであることを、詳しく説明してください。
Q. ランニング・ハイがゾーン(=フロー)の一種であることを詳しく教えてください。
畑さんには、サッカー選手時代の自らのゾーン(フロー)体験をもとに、保健体育におけるシン高生のフローの探究学習を伴走(ファシリテート)していっていただけたらと思います。
このようにシン高では、ファシリテーターが自らの体験をもとに、生徒の探究学習に伴走します。
それが教育(きょういく)ではなく共育(きょういく)の意味です。
3.脳と運動
さて、シン高における共育は、構築主義に乗っ取っていなければなりません(『eSOM』(15)参照)。
全教科における探究学習は、生徒一人ひとりが自分にとって必要なものを構築するために行われます。
家庭科で構築するものは、「バガボンドへの道(=フロー(ゾーン)な仕事への道=自分自身のウェルビーイングへの道)」、つまり「人生の設計図(ロードマップ)」でした(『eSOM』(15)参照)。
それを踏まえて体育の授業では、自らの身体そのものを構築するために、色々と探究していきます。
ウェルビーイングな身体がなければ、「バガボンドへの道」をゆくことは出来ないですからね(ウェルビーイングについては『eSOM』(15)参照)。
そして、「バガボンドへの道」のゴールは、「フロー(ゾーン)な仕事」をして一生過ごせることでした。
となると、身体の中でも、フロー(ゾーン)に関係する部分の構築が特に重要ということになります。
それは脳です。
そして脳の構築の手引きとなるのが、アンデシュ・ハンセンが著わした『運動脳』です。
それゆえシン高では、『運動脳』が保健体育のメイン・テキストになります。
『運動脳』の最も重要な点は、極めてシンプルです。
運動(特にウォーキングかランニング)が、フロー(ゾーン)に入り、その状態を維持し易い脳を作る。
それだけです。
それを精神科医である著者ハンセンが、科学的に綿密に、かつ、非常に分かり易く説きます。
ウォーキングかランニングがフローな脳を作るとなると、ウォーキング/ランニングに適した身体を構築しなければなりません(ウェーキングよりランニングのほうがフローに適した脳の構築に効果があるそうです)。
こうして結局、脳も含め身体全体を構築しなければならないことになります。
そのための指南書として、『運動脳』に加え、シン高生全員が購入した大修館書店の教科書『現代高等保健体育』が役に立つわけです。
4.体育:第一回目スクーリング
5月第3週目から始まるスクーリング第1回目は、ファシリテーターがここまで話したら、第2回目のスクーリングまでに各自、自宅でこなすべき課題の説明です:
-
まず、第一回目の体育のスクーリング後、宮本武蔵が著わした『五輪書』の「空(くう)の巻」と、アレキサンダー・ベネット(関西大学国際部教授)による解説を読んでいただきます。
-
この解説でベネットは、武蔵の言う「空」が、シン高における最重要概念であるミハイ・チクセントミハイのフロー(ゾーン)と通ずることを説いています。
-
これと同じものを、書道と言語文化の第一回目のスクーリングでも読みます。
-
フロー(ゾーン)=空を理解したうえで、次回のスクーリングまでの間、毎週、最低2回、1回につき最低30分のウォーキングかランニングを行い、そのアプリの記録をスクリーンショットで撮っておきます。
-
そして、そうした定期的なウォーキング/ランニングが、自分の身体と脳にどのような影響を及ぼしたかについてレポートを書き、アプリの記録のスクリーンショットとともに提出します。
-
第二回目のスクーリングに向けて、『運動脳』第一章「現代人はほとんど原始人」と第3章「「集中力」を取り戻せ!」を予習として読んでおきます。
5.体育:シラバス(授業概要)
全四回ある体育のシラバス(授業概要)は以下の通りです(注:授業の進捗状況により変更する場合があります):
-
スクーリング第1回 フロー、脳、運動
-
第2回までの間にやるべきことの説明
-
ウォーキング/ランニングとレポート作成(上記参照)
-
レポートと共にウォーキング/ランニングの記録を提出(記録方法、提出方法、提出先をシラバスに明記)
-
予習課題
-
宮本武蔵『五輪書』(コピー配布)
-
『運動脳』第1、3章
-
スクーリング第2回 フローのための脳の構築(『運動脳』第3章)
-
第3回までにやるべきこと
-
ウォーキング/ランニングとレポート作成
-
レポートで答えるべき問いはスクーリング内で配布
-
予習課題
-
『運動脳』第2章
-
スクーリング第3回 フローの天敵1:ストレス(『運動脳』第2章)
-
第4回までにやるべきこと
-
ウォーキング/ランニングとレポート作成
-
予習課題
-
『運動脳』第4章
-
スクーリング第4回 フローの天敵2:鬱(うつ)(『運動脳』第4章)
-
最終レポート提出までにやるべきこと
-
ウォーキング/ランニングとレポート作成
第3回目、第4回目のテーマは、ストレス、鬱という思春期に陥りやすく、かつ、現代において世代を超えて多くの人々を悩ます課題を探究し、その解決法を探ります。
このように、シン高における学びの全ては、人間が直面する実際の課題の解決に向けて、何かを構築するためのものです。
そもそも学びとは、そうしたものとして、誰もが生涯に渡って行うべきもののなずです。
シン高ではそれを実際に行いながら、高校生のうちに身体に刻み込んでいきます。
6.論述力としてのコンピュテーショナル・シンキング
どのような課題に直面しても、その解決に役に立つ構築物が、コンピュテーショナル・シンキング(計算論的思考)です。
コンピュテーショナル・シンキングというと難しく聞こえますが、恐るるに足らずです。
Q. コンピュテーショナル・シンキングを、高校生がワクワクしてもっとそれについて学びたいと思えるような具体的を用いて、明確かつ詳しく説明してください。
シン高では、まず入学早々に、コンピュテーショナル・シンキングについて学びます。
そしてそれから卒業までの間、ほとんどの教科で課せられるレポート作成というかたちで、コンピュテーショナル・シンキングを培っていきます。
良い文章は、コンピュテーショナル・シンキングの反映だからです。
Q. 良い文章は、それ自体がコンピュテーショナル・シンキングの反映とよく言われますが、それは具体的にどういった点においてそうなのかを、コンピュテーショナル・シンキングの4つの要素に沿って、順序良く詳しく説明してください。
とは言え、コンピュテーショナル・シンキングとは何かを完全に理解してから、それに基づくレポートを書こうとすることは構築主義に反します。
構築主義のモットーは、まず構築し始め、その実践を通して学んでいくです。
そしてその実践が、出来る限り効率よく学ぶべきことの習得につながるよう工夫するのが、ファシリテーターの役目です。
シン高におけるそうした工夫は、次のようなものです。
体育のスクーリング第二回目に出題されるレポートの問いは以下のようになります(注:変更の可能性があります):
-
『運動脳』113~144頁を読み、報酬系、側坐核、ドーパミン、運動、前頭葉がどのように関係し、集中力(≒フロー≒ゾーン)が高まるかを説明してください。
-
回答は、300文字以上、400文字以下で書いてください。
-
情報の一つひとつに、どこの頁に書かれているかを以下の例のように注記してください。
-
例:「報酬系」というシステムは、人間をある種の行動へと駆り立てる動力源である。(『運動脳』、125頁)
この問い(課題)の回答をレポートとして書くことが、どうしてコンピュテーショナル・シンキングのトレーニングになるのでしょうか?
まず、情報一つひとつに出典箇所を注記しなければならないので、AIの回答をそのままレポートとして提出するわけにはいきません。
この問いをプロンプトとしてAIに入力すれば、容易に回答を得ることが出来ます。
Q. 報酬系、側坐核、ドーパミン、運動、前頭葉がどのように関係し、集中力(≒フロー≒ゾーン)が高まるかを説明してください。
しかし、どの情報が本のどの頁に記載されているかまではAIは答えてくれません。
そしてこのAIの答えは、『運動脳』113~144頁に、AIとは異なる表現で書かれており、しかも異なる配列で表記されています。
さらには、1300文字以上のAIのこの答えを、400文字以下で書かなければなりません。
従って、AIが回答の指針を与えてくれるとは言え、出題の指示通りに書こうとすれば、「分解」、「パターン認識」、「抽象化」、「アルゴリズム設計」というコンピュテーショナル・シンキングの4つの要素が駆使されなければなりません。
出題の指示に従い、適切な回答を書くうえで、どの要素がどの部分に該当するかを探求することも、コンピュテーショナル・シンキングのトレーニングになるでしょう。
またこのようなAIの使い方をすれば、AIが思考力を弱めるどころか、コンピュテーショナル・シンキングという、AIの時代に最も求められる思考力のトレーニングに最適な伴走者となるでしょう。
すべてはファシリテーターの伴走(出題、添削、ファシリテーション)の仕方にかかっているということです。
(続く)