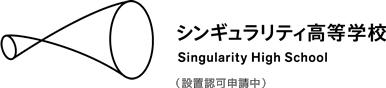eSOM (イゾーム)
eSOM (イゾーム)
Dへの道、あるいはシン高と幸和の物語
(小説)「Xへの道」、あるいはシン高物語(20):「ぼくの好きな先生」柄谷行人と「僕らの夏の夢」
1.
14歳の君(僕)へ、そしてシン高のみんなへ
たった今、Xに次の投稿をしたばかりだ(太字はXへの投稿):
·10 Views
というわけで、以下はなぜこの曲がシン高のテーマソングかの説明だ。
前回(小説19)をアップしたのが、8月20日(火)10:12AM。
その前日に僕は、小説18(セクション8)で登場する哲学者・柄谷行人さんを訪ねた。
彼は多摩丘陵の自然の中で暮らしている。
盆と正月、会津への帰省の道中、必ずそこに彼を訪ねる。
それ以外でも、東京に用事があり、時間の余裕がある時はそうする。
別に特段用があるわけはない。
今からちょうど30年前の1994年2月25日(金)、ニューヨーク州のイサカという田舎町で初めて出会って以来、ずっとそんな感じだ。
しかし会うと彼は必ず、脈略もなく独り言のように、僕が「Xへの道」を往くうえでのヒントを呟いてくれる。
預言者のように。
今回もそうだった。
僕ら二人は食卓に座っていた。
奥様は台所でお茶を入れていた。
しばしの沈黙。
いきなり彼は言った。
「遠藤君は広島へ行くべくして行ったな。あそこは世界史と日本史、両方の中心だ。」
僕はそれが何を意味するか即座に直観できた。
しかし「ああ…」と返事にならない返事しか出来なかった。
この柄谷さんの言葉の意味が、この『(小説)「Xへの道」、あるいはシン高物語』そのものだからだ。
この物語は、柄谷さんと、僕と、僕の仲間たち(「シン高のみんな」)の物語だ。
2.
柄谷さんに会った後、新旧のシン高の仲間に会った。
これから仲間になって欲しい人の作品展も観に行った。
21日(水)の午後の便で広島に戻った。
『ヴィンランド・サガ』を第六巻まで読んだ。
それから24日(土)の被爆伝承者研修での「沖縄の被爆者たち」(『この世界の片隅で』所収)に関する発表の準備をした。
23日(金)の夜は、希代のジャズピアニスト・大林武司さんのライブを聴きに行った。
大林さんは、「この世界の片隅で」流れるジャズを継承している。
その話はまた今度しよう。
いずれにせよ、多摩丘陵で柄谷さんに会ってからのこの一連の流れは全て、彼が発した「金言」に収斂する。
それがどういうことかを君に伝える。
3.
それを伝えるにあたって、色々な始め方が浮かんでいた。
けれど、27日付けの「日経新聞」朝刊を開き、以下の三つの記事から今回の物語を始めることにした(太字はXへの投稿部分):
·17 Views
朝刊を開くと、まずこの記事が目を引いた。
その理由をコメントとして添えたが、それを以下のようにもう少し詳しく書いてXに投稿した:
·10 Views
要は、基幹産業における商品生産が、人間に幸福、不幸のどちらももたらすということだ。
そうして世界史は動いていくということだ。
ある国の人間の幸福が、他の国の人間の不幸の上に成り立っているということだ。
果たしてその繰り返しを止めることが出来るのかということだ。
まず僕、商品生産と人間の幸不幸の関係を理論としてではなく、金型・部品や半導体その他電子部品会社の取材を通して学んだ。
その後、大学院に戻り、なぜそうなるのかの理論と歴史を学んだ。
一番役に立ったのは、コーネル大学歴史学科名誉教授のウォルター・ラフェーバーの『日米の衝突 ペリーから真珠湾、そして戦後』だった。
そこには、石油という商品と、その商品を使って生産した商品を売るための市場への「欲」が一大要員となって戦争が起こり、その後、自動車とエレクトロニクス製品という商品を巡って再び「貿易戦争」という名の戦争に突入し、「二度目の敗戦(=失われた30年)」が色濃くなるまでの歴史(~1993年)が描かれている。
「失われた30年」を「二度目の敗戦」とする見方には賛否両論あるようだ。
ラフェーバー先生の本を読むと、「賛」の側につきたくなる。
いずれにせよ、ラフェーバー先生の世界史と表裏をなすのが、以下の「戦後70年談話」と言えるだろう:
·36 Views
「ラフェーバー先生の世界史(=『日米の衝突』)」と照らし合わせると、「戦後70年談話」には色々と突っ込みどころがある。
けれど大いに賛同すべき点があり、それが最も重要だ。
「(8)戦後日本は世界平和、世界秩序の忠実な支持者だったが、さらに大きな役割を果たすべきである」という点。
そして
「(9)過去の歴史をしっかり記憶に刻むことが重要である。そのため、近代史教育のあり方に大きな改革が必要である」という点だ。
一言で言えば、「日本は世界平和、世界秩序」のために「さらに大きな役割を果たすべきであ」り、「そのため、近代史教育のあり方に大きな改革」をもたらし、「過去の歴史をしっかり記憶に刻むことが」「必要である」と言う事だ。
これを僕も含めシン高のみんなでやる。
それが「僕ら(シン高生)の世界史」だ。
僕らは、長崎とともに世界で唯一、人類そのものを根絶しかねない原爆を経験した広島で暮らす者として、その使命を担っている。
大変だけど、やりがいのある使命だとは思わないかい?
そして柄谷さんが「水先案内人」だ。
8月6日に生まれた彼も、同じ星の下に生まれたのかもしれない。
そんな「僕らの世界史」は、柄谷さんが唱える「X」という名の「僕らの夏の夢=ヴィンランド=世界平和、世界秩序」を目指す。
そこには
「敵などいない 誰にも敵などいないんだ
傷つけてよい者など どこにもいないんだ」
この「Xの真実」を僕は、石巻市震災遺構大川小学校で知った。
それはまさに
「瓦礫の街の小さな花
健気に咲くその一輪」
(”to U” by Bank Band with Salyuより)
のようだ。
導いてくれたのは「ジョンの魂」と「坂本龍一と高谷史郎のアート」であった(小説(15),(19)参照)。
4.
「ラフェーバー先生の世界史」は1995-6年で幕を閉じる。
そこから今(2024年)に至るまでの日本の「失われた30年」の間に世界では何が起きたか。
それを、昨日Xに連続投稿した日経の記事と、それに附した僕の注釈が如実に物語る。
一言で言えば、自動車のEV化に象徴される中国の台頭だ:
·11 Views
「素材加工の部品メーカーにとって、需要先の約7割は自動車だ。自動車のEV化が進めば、エンジン車で3万点ある部品のうち1万点が不要になるとされる。」 「脱炭素化の流れは変わらないとみられ、海外でも素形材産業が自動車以外の分野に進出する例が増えている。」
·10 Views
·17 Views
·12 Views
半導体新素材を国内量産:日本経済新聞
EV向け出遅れ、官民で巻き返し ロームは基板内製化
·19 Views
·10 Views
「日本勢は投資競争で出遅れており、日本の半導体メーカーでもSiC基板は9割超を海外に依存している。これ以上の遅れを防ぐため、官民あげて供給網づくりが進み始めた。」
こうして、「電力の変換効率」といった技術一つで、国民全体のウェルビーイング(幸せ)度が決まって行くんですね。
·15 Views
こうして「技術」は長い間、人間のウェルビーイングの一大決定要因であり続けてきました。時には、それを他者から盗んだり奪ったりというかたちで、人間の悪い面を露呈させながら。だれもがその恩恵を被れるようにするにはどうしたらいいか?
はみんなでそれを考え、実現していきたいと思います。
·7 Views
5.
以前から僕は、いかに一時は世界を席巻した日本の自動車産業が、中国をはじめとするEVの台頭で危機に陥ってるかについての記事をXにアップしていた。
このところも相変わらずEVとAIが日経の紙面を賑わしている:
·12 Views
・
、
で全面提携 基幹部品など、
市場で巻き返し – 日本経済新聞
·30 Views
領空侵犯「重大な主権侵害」 防衛相が批判、中国は意図否定
·13 Views
·8 Views
(続く)