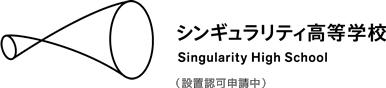eSOM (イゾーム)
eSOM (イゾーム)
Dへの道、あるいはシン高と幸和の物語
(小説)「Xへの道」、あるいはシン高物語(12):8.12.2024震災遺構大川小学校「おかえりプロジェクト」
14歳の君(僕)へ、そしてシン高のみんなへ
9日(金)から、今(1981年)君が暮らしている会津(福島)に帰るよ。
そして11日から13日にかけて、宮城県石巻市大川地区で開催される震災遺構大川小学校「おかえりプロジェクト」に参加する。
去年の「おかえりプロジェクト」についてはこちら
↓
今(2024年)から13年前の2011年、「東日本大震災(3.11)」が起こり、2万2325日本の死者・行方不明者を出す(広島原爆の推定死亡者数14万人、長崎7万人)。
君にとっての今(1981年)から30年後、現在14歳の人が1歳の時だ。
「おかえりプロジェクト」に参加することになったきっかけは、日上雅義という高校の先生に出会ったこと。
3.11後、東北の被災地に生徒を連れてボランティア行っていた日上先生は、シン高HPの「校長からのメッセージ」を読んで連絡をくれた。
シン高の「校長からのメッセージ」として僕は次のように書いた:
「校長からのメッセージ」
私は、文字通り教育に生かされてきました。
私は高校卒業直後の18歳の時に、福島県の山奥(会津地方)からニューヨーク・シティ(NYC)にいきなり跳びました。 それまでの私は、昼間に通っていた学校の勉強が退屈で仕方ありませんでした。 一方、夜中に聴いたり読んだりするラジオや本が教えてくることには興味津々で、そこから沢山のことを学びました。 日本を離れる前の私にとっての真の学校とは、夜な夜な宇宙を駆け巡るラジオ電波で出来た「ラジオの時間」でした。 そんな素敵な学校での一番の「ぼくの好きな先生」は、ジョン・レノンと坂本龍一でした。
それゆえ高校卒業直後、ジョンが眠り、坂本さんが暮らすNYCに跳んだというわけです。
NYCに滞在するためだけに入学した大学は、日本の学校とはうってかわって楽しいものでした。 まるで「ラジオの時間」が現実世界に現れたようでした。 私は興味がある授業を片っ端から取り、学部も理系文系を越えて数回変わりました(米国の大学ではそうしたことが可能なのです)。 そうしているうちに私は、私の人生を一変させた先生に出会い、彼の勧めで大学院に進学し、いつの間にか北米で大学教授になっていました。
大学院に進学して一番良かったことは、博士号を取ったことでも、大学教授になったことでもありません。 今に至るまで私の人生を彩ってきた友だちや先生に出会えたことです。 今では世界的に著名な大学の教授になっている人も含め、そうした私の人生の「宝」と共にシン高を作っていきます。
2011年、私は当時務めていた大学で、北米で教授職を得たものなら誰もが目指すテニュア(終身在職権)を取得しました。 同年3月、故郷の福島を東日本大震災が襲いました。 卒業式シーズンでした。 インターネットから流れる地元のラジオ放送が、亡くなった方々の中には、卒業を間近に控えた人も大勢含まれていたことを伝えました。 渡米する前、良く聴いていたラジオ局でした。 それを聞いた私は、取得したテニュアを捨て、30年ぶりに日本に戻って学校を作ることを決めました。
そんなふうにして始まったシン高には、私が米国で経験した「学校の素晴らしさ、楽しさ」のエッセンスを全て詰め込みたいと思っています。 そのエッセンスとは「好きな友や先生と、楽しくワクワク感一杯で学んでいるうちに、いつの間にか明るい未来が開けてくる」ということです。
シン高をそんな学校にしていこうと思っています。
シンギュラリティ高等学校 校長遠藤 克彦
これを読んで日上先生は連絡をくれた。
3.11、そしてジョン・レノンのくだりが刺さったらしい。
日上先生もジョンが好きだそうだ。
日上先生は2014年の土砂災害後、広島でもボランティア活動をしていた。
安佐南区の慰霊碑のある辺りを案内してくれながら、彼は僕に当時の様子や活動のことを色々と教えてくれる。
その話を聞きながら「この人はまるでジョン・レノンのようだ」と思った。
彼の紹介で震災遺構である大川小学校に向かう僕に彼は、以下のようなメッセージをくれた。
そこには「ジョンの魂」が宿っている。
「日上先生からのメッセージ」
ひとつ、先生にお伝えしておきたいことがあります。
「Team大川 未来を拓くネットワーク」は、大川小学校で生き残った生徒、妹や弟を亡くした卒業生、そして彼らを震災直後からサポートしてきた同年代の若者からなる団体です。現在、Team大川代表の只野哲也くんは、5年生の時、あの場所にいて、奇跡的に助かった4名の生徒の一人です。
3月11日の地震発生の直後、先生や生徒たちは高台に避難することなく50分間も校庭にとどまり、津波が到達する2分前にやっと避難を始めて、74名の生徒と10名の先生が津波に飲み込まれて亡くなりました。
哲也くんは、避難する途中、津波で家々が壊れて土煙を上げるのをみて、山側に向かって走って逃げたそうです。すると途中で背中にドンと衝撃を受けて、そのまま気を失い、気がつくと山の中腹に打ち上げられていたそうです。その晩は、助かった他の生徒や先生らと、山中で過ごし、夜明けとともに、山を越えて安全な場所に避難することができました。
一緒に小学校に通っていた妹さんは同じ場所で津波にのまれて亡くなり、母親と祖父も津波で失っています。被災後に、メディアの前で気丈に振る舞う哲也くんの姿を何度か見たことがあります。テレビの前で自分の体験を証言することは、小学生の哲也くんにとってほんと大変なプレッシャーだったと思います。
先生もご存知かと思うのですが、東日本大震災発生直後、多くの学校では、集団で高台に避難して児童生徒は無事だったのですが、大川小学校では、避難が遅れて多くの小さな命が失われました。学校の裏には数分で登れる山があったので、保護者のみなさんは、子どもたちがそこに避難しているとばかり思っていたそうです。
そこで、ご遺族は、震災前の学校の防災体制に不備があったとして、宮城県と石巻市を相手に裁判を起こしました。当時その損害賠償額(23億円)だけがセンセーショナルに伝えられ、その間、ご遺族、そして生き残った生徒たちは誹謗中傷にあい、哲也くんも、しばらくはメディアから遠ざかることもありました。さまざまな苦労があったことと思います。
2019年、最高裁は県と市の上告を退け、約14億3600万円の支払いを命じた二審・仙台高裁判決が確定しました。震災の津波被害をめぐり、公共施設を管理運営する側に、事前対策の不備を認めて賠償を命じた、画期的な判決となりました。その判決を受けて、日本全国の小中高校では、改めて防災教育の重要性の周知と、避難計画の見直しが行われました。
大川小学校で犠牲となった子どもたちの保護者のみなさんの取り組みが、日本の教育を大きく変革させたということ、意外とこの事実を知らない教員は多いと思います。
ボクが初めてTeam大川のみんなと出会ったのは2016年5月、広島の中高生を引率して大川小学校を訪れた時です。ちょうどこの頃、大川小学校を震災遺構として保存するかどうか、賛否両論が渦巻く中で、Team大川のみんなが保存の意見表明を行った時期と重なっていました。その後、大川小学校が震災遺構として保存が決まりますが、彼らの声が、行政を動かしたのでした。
そして、その年の夏休み、原爆記念日に合わせて、今度はTeam大川のみんなが広島を訪問してくれました。戦後、取り壊されることになっていた原爆ドームが、当時中学生だった少女の手紙がきっかけで、保存へと大きく流れが変わったという歴史があります。原爆ドームと大川小学校の校舎を重ね合わせて、広島の保存運動を学びに来てくれたのです。
ボクが初めて哲也くんと会ったのは、2017年12月、東京で開催された講演会でした。大学進学を控えた高校3年生の哲也くんは、柔道で鍛えたがっしりとした体格になり、参加者の質問にに対して丁寧に自分の思いを述べることができる青年に成長していました。
その後、何度か、広島から大川へ、大川から広島と、交流を続けました。そして2021年、哲也くんが、震災遺構大川小学校で伝承活動を始めることを決意し、被爆地ヒロシマからその伝承活動の取り組みを学ぶため、広島に来てくれました。これまで、さまざまな葛藤、挫折を経験してきたことと思います。被災後10年が過ぎてやっと話すことができたこともあると涙ながらに語る場面もありました。
2023年7月、ボクが勤務する高校で防災学習会を企画し、哲也くんに講師として話をしてもらいました。その時、「どうやって悲しみを乗り越え、伝承活動ができるよになったのですか」という高校生の質問に対して、まだ乗り越えることはできていないこと、今やっとスタート地点に立ったところだという哲也くんの言葉が、とても印象的でした。
たぶん哲也くんだけでなく、Team大川のメンバーみんなが、それぞれの悲しみやつらさを今も抱えながら、それでもなんとか一歩前進するために、苦闘している段階にあるものと思います。
そうした彼らの地道な取り組み、それを通して成長する姿を、時々そばで見せてもらいながら、ボクは勉強をさせてもらっています。そして、何かボクにもできることがあればやらせてもらおうと、損得勘定抜きで、そっと寄り添い、活動をさせてもらっています。
もちろん、ボクは、遠藤先生に、彼らの取り組みから新しい学校のヒントを得ていただきたいという思いがあります。しかし、それよりもまずは、彼らと友だちになってもらう、今回の訪問がそのスタートになればと願っています。
(終)
今回僕(君)は、シン高を代表し、「おかえりプロジェクト」の「裏方」に徹しお手伝いさせてもらうことで、Team大川のみんなと「友だち」なってこようと思う。
それにしても不思議なものだ。
「校長からのメッセージ」を読めば一目瞭然だが、僕は、シン高の前身である「ラジオの時間」を通して、福島からニューヨークシティ(NYC)に跳んだ。
そしてその32年後、同じ「ラジオの時間」を通してアメリカから広島に跳んだ。
福島、NYC、広島。
そのどれもが、僕(君)にとっての故郷だ。
この三つの故郷には共通点がある。
どれも被災地だ。
僕が伝承しようとしている被爆証言者の方は、3.11の映像をテレビで見た時、今も目に焼き付いている原爆投下後の広島の風景と同じだと思ったと教えてくれた。
僕は第二の故郷であるNYCがテロで破壊された時、そこにいた。
次回はその話からはじめよう。
(続く)